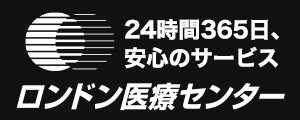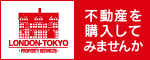第1回 夏の終わりに
9月も初旬になった。ロンドンから日本に戻って、ちょうど半年になる。
この間、日本では、いろんなことがあった。8月末には、自民党から民主党への「政権交代」を実現させた総選挙もあった。タレントの「のりぴー」が覚せい剤使用容疑で起訴されもした。ニュースの現場で仕事していると、半年前のこともよく思い出せないほど、世の中では種々のことが起きる。
そして、東京は名実とも夏が終わった。夜はクーラーもいらない。開け放した窓からは、虫の鳴く声も聞こえている。
ロンドン滞在中の、今の季節だったと思う。自宅近くの公園で、サッカーに興じる小学生の息子たちをぼんやり眺めていた。
広々とした緑の芝生に、それを取り囲む木々。空は高く、青い。高い建物が全く目に入らず、それが余計に公園を広く見せている。いかにも英国らしい風景だ。
半袖の子供たちは、10人ほどだった。この公園にいつも姿を現す、中東系の背の高い子供もいる。女の子もいるようだ。みんな夢中で走り回っている。
やがて、息子から「お父さん、レフェリーやって!」と声がかかり、木陰のベンチにいた私は「おう」と重い腰を上げた。そして、声のかかった方に歩き始めた。
実は、こういうとき、私はいつも「あの場面」を思い出す。「なぜだったのか」という疑問と、わずかな後悔を伴って。
40年近くも前の、高知の夏。
今の息子と同じような年齢だった私は、少し離れた繁華街へ自転車で遊びに行くことにした。高知市内とはいえ、中心部から離れた住宅街。街の真ん中へ行くことは、小学生の子供にすれば、ちょっとした冒険だった。
近所に住む同学年の友だち何人かと、約束していたのだと思う。途中で何人か合流し、最初の目的地だった高知駅へ。そこでさらに友人は増え、総勢で5、6人になっていた記憶がある。
すると、そこへ、父がやってきたのである。行き先を母に聞き、列車で2駅分を先回りしてきたのだという。父は子供たちを見回し、そして、こんなことを言った。
「みんなあ、きょうはどうする?何して遊ぶつもりやった?おじさんと一緒やったらゲームセンターにも行けるぜ。それか、冷たいもんでも飲むかえ?」
本格的なゲームセンターなど、世の中に登場していない時代のことだ。駅近くには、子供たちが「青屋根」と呼んでいたゲームセンターがあり、自分たちもそこへ行こうとしていたのだと思う。ゲームセンターと言っても、小さな倉庫を改造して青く塗り、ピンボールが数台置いてあるだけの場所だったが。
ところが、次の瞬間、私は父に向かって「帰って」と言った。
「お父ちゃん、帰ってや。きょうは僕らだけで遊ぶがやき。帰って、帰って」
しばらく、問答が続いた。友人たちは「お前、ええかえ?(それでいいのか?)」と口を挟む。それでも私は、戸惑う友人たちをよそに同じようなことを言い続けた。
やがて父は帰った。結局、何をして遊んだのかの記憶はない。
夕方、自宅に戻ると、母に呼ばれた。父の姿はない。
「昌幸、あんた、お父ちゃんに何を言うた?お父ちゃん、泣きながら帰ってきたぞね。あんなに悲しそうなお父ちゃんは見たことない」
声を荒らげるでもなく、叱りつけるでもなく。母は静かにそんなことを言い続けたように思う。
反抗期の始まりだったのかもしれない。子供たちだけの世界に、たとえ父とはいえ、大人が入り込むことがいやだったのかもしれない。あるいは、説明できる理由などなかったのかもしれない。
いま、私はあの夏の父と同じ年齢である。
ロンドンの公園で「レフェリーやって」という息子の声を聞いたときも、あの夏の出来事を突然思い出した。そして「お父ちゃん、泣いて帰ってきたぞね」という母の言葉は、一度思い出すと、なかなか消え去らないのだ。これを書いている今も。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?