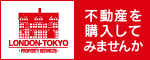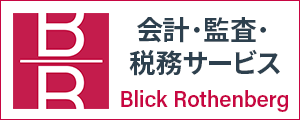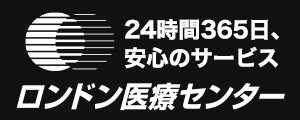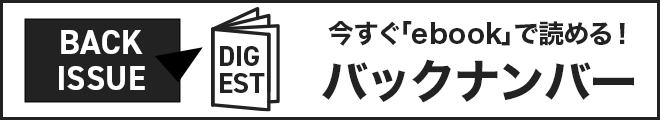英国における過小資本税制と過大支払利子税制の考え方
グループのコーポレート・ファイナンス再構築の一環で、子会社の資本金をグループからの借入に切り替えることを検討していますが、過少資本税制が気になります。
英国では日本のように出資と借入の比率による数的条件によって制限をするような税法はありません。過少資本税制では、ビジネスの実態を逸脱するような過剰な借入や、商業的に現実的でない高利率による借入が実施されている場合は、利子の損金算入が認められず、より原則ベースの制度であるといえます。つまり英国子会社は、会社間による借入が第三者間取引(Arm's Length)に相当することを証明する必要があります。通常は財務改善のためにデット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap=DES)といった借入を資本化する手法はよくとられますが、今回のような逆のケースでは背景や理由も説明できなければなりません。
具体的な数値による規制でないというのは、どのように対応すればよいのでしょうか。
これは移転価格とも密接に関係しており、商業的な観点から第三者間取引に相当するか否かを判断することになります。例えば、英国子会社が現地銀行から借入を行うと想定して、受けられる融資限度額や利率はベンチマークになるでしょう。ただし本社の保証が付く借入の場合は、子会社単体が第三者間取引として引き出した借入条件とはいえない点に注意が必要です。
言い方を変えれば、銀行から融資を受ける際に、銀行にビジネス・プランや財務状況の説明を行って融資枠や妥当な利率が設定されるのと同様に、英国子会社ビジネスにとって論理的なファイナンシングであること、経営者レベルでの適切な判断が行われておりこれらが文書化されていることが求められます。
過大支払利子税制についても、注意が必要でしょうか。
英国では支払利子について法人利息算入制限 (Corporate Interest Restriction=CIR)という税法があり、これが日本の過大支払利子税制に近いものといえるでしょう。CIRでは具体的な金額や条件によって利息の損金算入を制限しています。このルールは英国に存在する全てのグループ会社を含めて計算します。純支払利息が200万ポンドを超える場合は、損金算入として認められるのはTax-EBITDAの30パーセントまでとなり、これを超過した分は翌期以降に繰延されます。以前の記事でも触れましたが、このTax-EBITDAは税法上の特殊かつ複雑な計算で、企業が財務分析に使用するEBITDAとは異なります。なお、この制限され繰延された利子分については、時間的な使用期限は設けられず、消滅することはありません。昨今の利率の上昇によって、これまでCIR条件から外れていた英国グループが今期より新たに規制対象に入ることは十分に考えられますので、注意が必要です。
ほかに注意点はありますか。
英国から海外へ支払われる利子には原則として20パーセントの源泉徴収税(WHT)が課税されます。日英間の租税条約で、このWHTは0パーセントまで下げることができますが、自動的に免税が適用されるわけではありません。貸付主側で日英両税務当局からの承認を得るパスポート取得プロセス(DTTP1)を行い、その後借主側が英国歳入関税庁(HMRC)に該当ローンの通知(DTTP2)を行って初めて免税となります。もし手続き完了前に利子を日本に払ってしまった場合は、20パーセント分のグロスアップ(ネット額に対して25パーセント)分を納税することになります。
*この記事は一般的な情報を提供する目的で作成されています。更なる情報をお求めの場合は、別途下記までご相談ください。
 高西祐介
高西祐介
監査・会計パートナー
英国大手会計事務所にて多くの英系大企業監査を担当。日系企業をサポートしたいという強い思いからGBAへ。監査、ファイナンスデューデリ、組織再編アドバイスを専門とする。

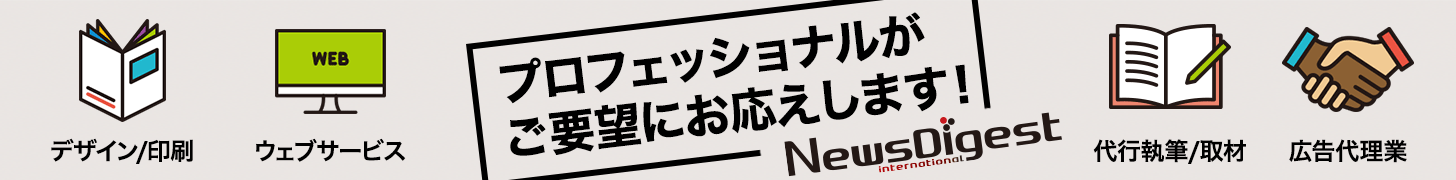

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?

 ジョン
ジョン イアン
イアン 浦崎
浦崎 廣田
廣田 トム
トム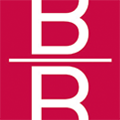 Blick Rothenberg
16 Great Queen Street, Covent Garden,
London WC2B 5AH
Blick Rothenberg
16 Great Queen Street, Covent Garden,
London WC2B 5AH