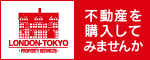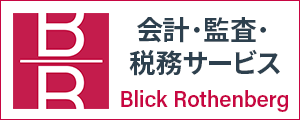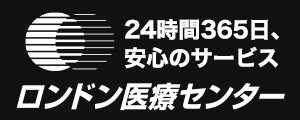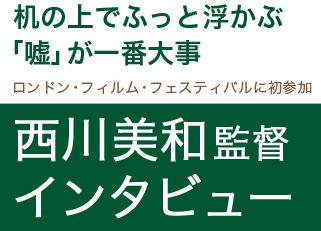
1974年7月8日生まれ、広島県出身。早稲田大学第一文学部卒。大学卒業後、是枝裕和監督の映画「ワンダフルライフ」の製作に参加。2002年に「蛇イチゴ」で監督デビューを果たす。2006年に発表した「ゆれる」がカンヌ国際映画祭に出品。長編第3作となる「ディア・ドクター」は、ブルーリボン監督賞を始めとする映画賞を多数受賞した。小説の執筆も手掛けており、2009年に刊行した「きのうの神さま」は直木賞候補に。ロンドン・フィルム・フェスティバルでの最新作「夢売るふたり(Dreams for Sale)」の上映に合わせて10月に渡英した。
Photo by Shinotsuka Yoko

監督としては初参加されたロンドン・フィルム・フェスティバル(LFF)についての感想をお聞かせください。
欧米では、つまらないと思うと上映中でも席をお立ちになってしまう方が結構いらっしゃるので、海外での上映ではいつもハラハラするんです。ロンドンの方は最後までじっくり観ていただけるお客さんがほとんどでほっとしました。LFFでは舞台挨拶の機会もあったのですが、観客の皆様はシャイで礼儀正しい方たちが多くて、日本人と共通している部分が少なくないのかなという印象を抱きましたね。
過去に観客としてLLFに参加されたことがあったと伺いましたが、そのころから本映画祭への参加を思い描いていたのでしょうか。
師匠である是枝裕和監督の「誰も知らない」がLFFに出品された際に、たまたま観光でロンドンを訪れていたので、その上映を一人の観客としてというか、ほぼ野次馬のような感じで観ていました(笑)。当時の私は監督デビュー作「蛇イチゴ」を撮り終えたばかりで、かたや「誰も知らない」はカンヌ国際映画祭で最優秀主演男優賞を獲得するなどして話題を集めていたので、是枝監督や、同監督と同じように世界各地の国際映画祭に出品している関係者の方々と自分が同じ土壌にいるとは到底思えなかったです。ただ是枝監督の映画がLFFで上演されているのを観たことで「確かな実績を築き、キャリアを積んでいけば、いつかは呼んでいただける映画祭なんだろうな」とは漠然と思いました。だから今回ロンドンにご招待いただいて、「ついにロンドンに呼んでもらった」というちょっとした感慨はありましたね。
この度LFFで上演された「夢売るふたり」の主な舞台として使われている居酒屋のシーンを見て、日本への憧憬を膨らませた英国人もいたのではないかと想像します。
「大衆的で、敷居が高くなく、どこにでもあるお店」という設定で居酒屋というシチュエーションを選びましたし、実際にほとんどの日本人観客にとっては居酒屋とはそういう存在なので、日本での上映であの場面設定について感想をいただくことはあまりないんです。ところがLFFでもトロント国際映画祭でも、あの居酒屋の風景に関しての感想だとか「食べ物がすごくおいしそうだった」と仰る方が結構いらして「へー、そこに反応するんだ(笑)」と意外な思いでした。
私自身は日本の風光明媚な風景や伝統文化を映画のセールス・ポイントにしているつもりはありません。むしろそうした風景や文化の中で暮らしている人々の生活や人生をしっかりと書いていくことができれば、周りの風景はどんなものでもいいとさえ思っているんですけれども。ただそうした人々の生活を描くために綿密な取材を行ったり、取材で集めた材料を映像の中に入れようとすると、自ずと風景のディテールが画面に映り込みますよね。結果的に、海外の観客の皆様には物珍しいとか日本的であると感じられる映像になるのかなあと思っています。
「夢売るふたり」の英題が「Dreams for Sale」に決定するまでの経緯を教えていただけますか。原題の中から「ふたり」が抜け落ちたのはなぜでしょう。
まず「夢売る」という言葉がそもそも本来の日本語としては存在しない言い回しですよね。何となく違和感を覚える表現というか。また同時に「夢見る」とか「夢得る」といった言葉をも潜在的に喚起するような、不思議なニュアンスのタイトルだと自分では認識しているんです。
ただ言語が外国語になった時点でそうしたニュアンスを厳密に再現するのはほぼ不可能です。それならば「夢売るふたり」というタイトルを逐語訳するよりも、そのタイトルが持っていた効果というかインパクトを同じような形で与える表現を英題にしたいと考えました。英語で「~ for sale」という言い回しが頻繁に使われていると思うのですが、本来は「dreams」と合わせては絶対使われない表現ですよね。その辺りのどこか不思議な言葉の組み合わせが醸し出す違和感が、「夢売るふたり」という原題のそれとつながると感じたので、このタイトルを採用することにしました。

西川監督にとって日本国外の観客とはどのような存在ですか。
私自身が外国の映画をたくさん観て育ってきたこともあって、映画というのは字幕や吹き替えさえ付ければ容易に国境を超えて交換できる文化だと信じています。そうやって自分の知らない地域の価値観、歴史、文化を知ることで日々を豊かにしていくことができるというのが映画の素晴らしさだと思っていますので。そうした「映画の循環」とでも呼ぶべき現象を止めることなく、その循環の流れの一つになりたいという願いはずっと持っています。私は知らない国の映画を観たいと常に思っていますし、自分の映画がその国名を聞いたことさえないような国で上演してもらえたらそれほどうれしいことはありません。
映画を製作する上で、日本人だけが観るのであれば必要ないけれども、海外の観客を意識するのであれば必要となる工夫などあるのでしょうか。
日本で映画をヒットさせたいということだけを考えるとなると、国内で知名度のある人を優先してキャスティングすることになると思います。ただそれは実は海外の人にとってはほとんど意味のないことですよね。例えば「夢売るふたり」に、ウェイトリフティングの競技選手という役があります。この役には、知名度のある体格の良いタレントさんにちょっとトレーニングして出てもらえれば、日本国内での展開においてはありがたいという考え方もあるんです。でも「そういうことではないだろう」という思いが自分の中にはあるので。だから、この役については一からオーディションさせていただきました。そうした判断も「映画はグローバルに広がっていくものだから」という考え方から生まれたものなのかもしれません。
世界的にいわゆる単館映画館が減少し、ロンドンにおいても欧州諸国や日本の映画作品を映画館で観られる機会が随分と減ったような印象があります。このような状況において、映画製作者には何が求められていると思いますか。
「映画製作者には何が求められているのか」というのは今でも日々考え続けていることなので……。ただ映画界において「新しいものを作るんだという意思」よりも「絶対に失敗しないものを作りたいという要請」の方が強くなっているという現状は確かにあると思います。そうした状況とどう戦っていくのかは、現在、映画を作ろうと思っている世界中の作家が共通して抱える悩みなのではないでしょうか。
私の場合は「作りたいものを作らせてくれる人が集まるまでは作らない」という方針を持っているので(笑)。自分が納得できるストーリーを書き上げられるまでは映画を撮り始めちゃいけない。そうした方法をずっと続けられる保証はないけれども、今後もそのスタンスは維持できたらと思っています。

前作の「ディア・ドクター」では、無医村医療の実態を調べるために泊まり込みの取材なども行っていたと伺いました。そうした綿密な取材活動を行われている一方で、西川監督の作品はそのフィクション性を高く評価されています。ご自身では現実とフィクションのバランスをどのように取ろうと意識されていますか。
私は映画を作る上で「嘘」をすごく大事にしています。もちろん現実の方がずっと過酷で、生々しくて、エキサイティングであるということは十二分に分かっているんですけれども、一方で嘘だけが人間が作れるもの。物語の中で嘘をどれだけ跳躍させることができるかという点が、作り手の勝負のしどころだと思うんですよね。現実世界への取材活動というのは、すればするほど発見が出てきますが、どれだけ取材を重ねても、それは創作物ではなくて単なる取材に過ぎないので。取材をしているとすごく仕事をしている気になってしまうのですが、その気持ちに溺れないように気を付けています。すべての材料がそろったときに、机の上で一人でじっと考えてふっと浮かんでくる「嘘」が一番大事。現実とフィクションの配分というものを計算したことはないですが、6対4でも5.5対4.5でもいいから、嘘の世界の方が分量が多くなっていなければいけないと思っています。
ご自身よりずっと年輩の役者さんや男性スタッフに指示を与えなければならない映画監督という立場を務めることでのご苦労も多いのではないかと察します。
20代で監督デビューを果たしたころは、男性の先輩ばかりを相手に仕事していたので、「穴があったら入りたい」という気持ちをずっと抱えながらやっていました。まあ、今も身の縮むような思いというのは全く変わらないんですけれども。ただチームの皆さんというのはプロの集まりですし、仕事というのは、他人が努力して培ってきた経験や知識をお借りしながら進めていくもの。俳優に対してもスタッフに対しても、相手への敬意というのが大切だと思っています。相手のキャリアと存在に対して常に敬意を払いつつ、一緒に前を向いていくにはどうしたらいいか。それは監督だけが示すことができる、その作品に対する確かなビジョンでしかないと思うのです。私の場合は自分で脚本を書いているので、その作品の本来のあるべき姿や目指すべき形を自分だけが知っているという確信を持つことができます。そこを頼りにしている部分があるので、逆に言うと自分で脚本を書かなくなると寄る辺がなくなってしまうのかもしれません。
世の中には男女両方の性別が存在するのが現実ですし、ありとあらゆる世代が共存しているというのが私たちが生きるこの世界ですよね。そういう環境で色々な意見を交換しながら、ぶつかりながらも助け合って、力を貸して、お互いを思いやるってすごく良い体験だと実感しています。その体験を味わいながら、楽しんでやっているつもりです。




 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?