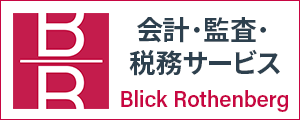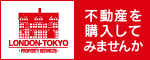「私には映画という『武器』がある」。映画というメディアを「武器」と呼び、その武器を手に政府や日本の現状と戦い続ける女性がいる。山田火砂子(ひさこ)監督、77歳。「はだしのゲン」実写版、「裸の大将放浪記」など、一貫して社会派作品に関わり続ける彼女が今月、一つの作品を携えロンドンにやって来る。作品の名は「筆子・その愛 ─天使のピアノ─」、石井筆子という実在の女性の半生を描いた映画だ。
(取材・文: 本誌編集部 村上 祥子)

東京生まれ。女性だけのバンド「ウエスタンローズ」のメンバーとして活躍後、舞台女優を経て映画プロデューサーとなる。プロデュース作品に「はだしのゲン」(実写版)、「春男の翔んだ空」など。アニメ映画「エンジェルがとんだ日」で監督デビュー。最新作「筆子・その愛─天使のピアノ─」に至るまで、一貫して社会派作品をつくり続けている。
日本のマザー・テレサ
「『日本のマザー・テレサ』である石井筆子をとにかく有名にしたい」。これがすべての始まりだった。幕末から昭和を生きた石井筆子は大村藩(長崎県)藩士(後に男爵)を父に持ち、時の皇后の命によりフランスへ留学。帰国後には社交界で「鹿鳴館の華」とも呼ばれた人物だが、華やかな経歴とは裏腹に、その存在を知る者はごくわずかだ。その理由は、波瀾万丈な彼女の人生の、日の当たらない後半生にある。自らが生んだ3人の子供のうち、2人が知的障害者、残る1人も虚弱児で生後まもなく死亡。また夫にも先立たれるなど、様々な苦難の末に、筆子は日本初の知的障害者教育施設「滝乃川学園」の運営に携わるようになり、再婚した夫の石井亮一とともに障害児教育という、当時の日本社会における影の部分に生涯を捧げたのである。
「こんな、日本のマザー・テレサとも言える人をほっぽらかしている日本の政府というか、学校というか、本来だったら学校の教科書ででも紹介すべきところを何にもしていない。戦時中、国は武器弾薬をつくることに夢中になっていて、障害者のように弱い人はものすごい差別待遇をされていたわけですよね。そういうなかで一人で戦ってくれた女性がいたので、頑張ってこの人の名を世に広めたいと思ったんです」
のっけから、辛らつな政府批判が始まった。あまり抑揚のない、ゆっくりとした一定のテンポで繰り出される言葉の数々は、穏やかな空気を纏いつつも、社会派映画だけをつくり続けているという硬派な印象を裏切らない鋭さに満ちている。
世に知られるべき人が知られていない、その現状に「ものすごく腹を立てて」石井筆子の映画をつくろうと決意した。独立系プロダクションの低予算作品。政府は「もちろん、一銭も出してくれない」から、ひらすら借金を背負っては返し、の日々だった。しかし、石井筆子という人物にほれ込んだという人気女優、常盤貴子が出演を快諾。そのほか歌舞伎俳優の市川笑也やベテラン俳優、加藤剛らそうそうたる顔ぶれが揃った。また石井筆子夫妻が日本聖公会の信者だったことから、同じ日本聖公会に属する立教女学院が学校や教会を撮影場所として提供。知的障害者の子供を持つ親の会などからの支援もあり、なんとか完成までこぎつけた。
完成後は自らホールを借りたり、フィルムの貸し出しを行うなどして「日本列島縦断の上演運動」を敢行。また、各地でこの映画を観て心を動かされた人が次の地へ作品を紹介するという、草の根的な広がりも見せた。封切後、数カ月が経った2007年11月には、ダウン症の子供を持つ在米の主婦が中心となり、米ロサンゼルスでの上映を実施。ロンドン上映も、同作を観て心を動かされた一人の在英邦人がきっかけとなった。「イギリスは聖公会が国教ですよね。筆子さんは聖公会の信者だったし、ヨーロッパに長いこといた人だから、故郷に帰るような気持ちなんじゃないかしら」と山田さんも今回の上映には格別の思いを抱いているようだ。

情熱を支え続る一人の存在
現在、77歳。撮影現場では杖をつき、時には車椅子を使うこともある山田さんをここまで駆り立てたものとは、果たして政府への怒りと石井筆子への敬慕の念、それだけだったのだろうか。実はそこには、山田さんの情熱を支えるもう一つの存在があった。山田美樹さん。重度の知的障害を持つ、山田さんの長女である。
「 今、娘は45歳になりますけれども、生まれた当時は福祉なんて言葉すらない時代でしたから、大変な思いをして育てました。なにせ学校にも入れてくれなかったんですよ。日本の恥部の時代ですから」
山田さんは16歳で女性バンド「ウエスタンローズ」のメンバーとして活躍。25歳で女優に転身し、29歳で結婚。順風満帆な人生だった。その華やかな日々が思ってもみなかった形である日突然、終焉を迎える。結婚直後に誕生した長女美樹さんが2歳になる直前に、障害を持っていることが判明したのだ。今でこそ福祉制度の充実を目指し、積極的に働き掛ける山田さんも、当初はひたすら負の感情に苛まれた。
「障害の子供なんて、ぜーんぜん、知らなかった。最初はとにかくびっくりして、恥ずかしい、嫌だと思っていました。それを乗り越えてこの子のために何かしなきゃって考えるようになったんです」
「頭の良くなる薬ができないものか」と悩んでいたのが、やがて「この世にはいらないものなんてないんだ。この子たちも必要だから生まれてきたんだ」と考えるようになった。そのマイナス思考をプラスへと転化させたのは、劇的な事件ではなく、美樹さんと日々を暮らすうえで起こった小さな出来事の積み重ねだったという。
「とにかく心がきれいなんですよ。人が嫌がることでも平気でやってあげるし。それなのにデパートで前の奥さんが着物の反物なんかをストーンと平気で落としていくのをあわてて行って拾ってあげて、デパートの店員に『あんたたちがいるから困るのよね』なんて言われているのを見ると、なんでこんなひどいこと言われなきゃいけないのって思うようになるでしょ。そういうことを繰り返しているうちに、だんだん自分の持っていた『障害者を恥ずかしい』と思う固定観念の方が負けていくわけです。自分はなんてくだらない人間だったんだろうと考えるようになるんですよ」
美樹さんが小さな頃は、他人に美樹さんを見せることが嫌で家の中に隠していた。でももし美樹さんが「利口」だったら、相手が何も言わないうちから「見てくださいな」と言って自分から寄っていっただろう。優越感に浸りたい人こそ、劣等感に沈むことになる。山田さんは美樹さんを通じて、「優越感と劣等感は表裏一体であり、そんなものにこだわっているのはくだらない」と気付かされた。今では美樹さんのことを「自分の先生」であると考えている。障害者の子供を持つ母親は、「必死になって育てた」人ならば誰もが同じことを言いますよ、と語る山田さんの声はいつしか、社会派映画監督ではなく、自分の子供を愛おしむ一人の母親のそれになっていた。
社会的弱者を世の光に
次女有さんが誕生後に離婚、1人で喫茶店を経営していた山田さんは、やがて映画監督の山田典吾さんと再婚。その後は何も知らぬままに典吾さんが監督を務める作品のプロデューサーを務めるようになる。障害者の子供を育てていくだけでも並大抵の苦労ではなかった時代に、再婚後も働き続けようと思ったのは何故なのか。
糸賀一雄先生*という方がいて、『この子らを世の光に』とおっしゃっていたんです。『この子らに』じゃなくて『この子らを』。この言葉を聞きまして、この子たちを世の光にするには世の人々に知ってもらわなければならない、そのためにはテレビや映画が必要だと思ったんです」
山田さんは、社会的弱者と呼ばれる人々を「光」にしようと典吾さんと意気投合。プロデューサーとして、そして平成10年に典吾さんが死去した後は監督として、ひたすら原爆被害者や知的障害者など、社会的弱者と呼ばれる人々を題材とした映画をつくり続けた。そして今後もずっと、そのスタンスを変えるつもりはないと語る。
「映画は何でも好きですよ。でも自分がやるのは社会的テーマのあるものだと。それが自分の役目だと思っているんです。もちろん、娯楽も必要ですよ。でも私がつくらなくても、もっと素晴らしい監督の方たちがいくらでもいらっしゃる。だから私にできることはこれしかない、そう思ってこのテーマを追い続けています」
*糸賀一雄: 戦時中の1946年、知的障害児と孤児のための施設「近江学園」を創設、日本の障害者教育の発展に一生を捧げた。
「映画という武器」を手に
高齢化・少子化社会を迎える今、福祉制度の必要性は、誰もが認めるところだろう。しかし頭では重要だと分かっていても、その意味を心から理解するのは難しい。国が富むことが何よりも優先された戦時中、そして国民一人一人の生活が不安定さを増す不況下。人間は自らの基盤が危うくなると、他人のことを顧みる余裕を失うものだ。石井筆子、そして山田さんが福祉に対し並々ならぬ情熱を持ち続けることができたのは、やはり自らの子供が障害を持っていたという事実が少なからず影響しているはずだ。では障害者が自らの身近にいない人間が、こうした意識改革を起こすことは可能なのだろうか。こんな少し穿った質問に、山田さんは間髪入れず「可能だと思います」と答えた。
 「30年くらい前に『春男の翔んだ空』っていう映画をつくったんですが、そのときには健常の子供が障害者の子供を嫌がって手を引っ込めたりしていましたけどね。でも今回は手をつないで、ほっぺたをくっつけ合って仲良く撮影をしてました。時代は変わったなあって思って、本当に嬉しかったです」
「30年くらい前に『春男の翔んだ空』っていう映画をつくったんですが、そのときには健常の子供が障害者の子供を嫌がって手を引っ込めたりしていましたけどね。でも今回は手をつないで、ほっぺたをくっつけ合って仲良く撮影をしてました。時代は変わったなあって思って、本当に嬉しかったです」
知的障害者施設を舞台にした本作で、山田さんは健常者の子役とともに実際の知的障害者たちを役者として使っている。顔を洗うシーンで、突然たらいに顔を突っ込んで、ばしゃばしゃと水をはね散らかしたり、太鼓を叩きながら歩くシーンでは、楽器を持たない子が自分の頭をポンポン叩いてリズムをとったり̶̶彼らは時にアドリブを入れつつ、とにかく自由奔放に、生き生きとした「演技」を見せた。
もちろん、一筋縄ではいかない部分もあった。送迎バスが気に入って、外へ出ようとしない子がいるかと思えば、食事のシーンでは隣の子のご飯を奪って食べている子もいた。でもそんなハプニング続きの日々の中には、忘れられない思い出となった印象的な出来事もある。
「 けんかのシーンを撮っている時、一人の男の子が出ないと言うんです。「アメリカに帰れ!」とみんなでいじめるところで、どうしても出ない、けんかは嫌だって。結局この子はそのシーンには出ませんでした。そのシーンの撮影が終わった後に、いじめられる役の子、健常者の子役だったんですが、その子の方に行って、一生懸命手を撫でたりしてましたね」
生まれつき差別意識を持っている人はいない。だからこそ健常者の子供と障害者の子供が生活をともにし、互いを知り合うこうした機会は、山田さんが理想とする、障害者と健常者が区別されることなくともに生活する社会、ノーマライゼーションを実現する大きな一歩となる。知ること、それこそが健常者と障害者の垣根を取り払うきっかけになると信じる山田さんは、子供たちにこうした機会を与える一方で、大人たちに障害者のありのままの姿を見せる重要性を説く。
「 子供は順応するのが早いですからね。大人に差別の心があれば、子供も差別します。大人が変われば子供も変わるので、まずは大人に変わっていってもらいたいと思っています」
お金があれば、障害者と健常者がともに暮せる村をつくりたい。でもお金がないから「映画という武器」をフルに使って訴え続ける。山田さんにとって映画とは、夢の世界をつくり出す道具ではなく、現実の社会を映し出し、現実と戦うための唯一の手段なのだ。インタビューの最後、「年寄りだから言いたい放題言ってもわりとみんな怒らないけど、若い人だったら怒られちゃうかもしれないね」と笑いを含む軽い口調で言いながらも、「でもまあ、日本は住み良い国じゃないですよ」 とやはり辛らつな言葉で締めくくった山田さん。これからも彼女は映画の持つ力を信じ、制度や人々の心に巣食う差別心への憤りを原動力としつつ、日本全国、世界各地を「コトコトと」訪ね歩いて上演活動を続けていく。

筆子・その愛 ─天使のピアノ─
幕末の志士(後に男爵)を父に持ち、時の皇后の命によりフランスへ留学、帰国後には社交界で「鹿鳴館の華」とも呼ばれた才媛、石井筆子。何不自由なく暮らしていた彼女の生活は、知的障害者を生んだことで一変する。 夫に先立たれ、世間の偏見の目にも負けず子供を育てていく筆子は、やがて日本初の知的障害者教育施設「滝乃川学園」の運営に関わっていくようになる。
監督: 山田火砂子
出演: 常盤貴子、市川笑也、加藤剛ほか
上映イベント
A Contemporary Japanese Cinema and Art Festival
4月16日(木)15:00~
*同日16:45から山田監督のトーク・イベントあり。
詳細は下記イベント・スケジュール参照
英国在住邦人の高齢化問題に取り組むチャリティー団体、「Japan Care for the Elderly (JCE)」が主催する、日本の現代映画とアートを紹介するイベント。4月15~17日の3日間にわたりナショナル・ギャラリーで、「筆子・その愛―天使のピアノ―」をはじめ、アカデミー賞外国語映画賞受賞「おくりびと」や、北野武監督の「菊次郎の夏」などの作品を上演する。
「はだしのゲン」
 広島県に生まれ、6歳で被爆した漫画家、中沢啓治が、自らの体験を赤裸々に綴った同名漫画のアニメ映画化作品。1945年8月6日、広島県広島市に住む少年、中岡元は米国軍により投下された原爆により、父親や兄弟を失う。自らも原爆症の恐怖に苛まれ、身近な人々の死に苦しみながらも、元はたくましく戦後の混乱期を生き抜いていく。
広島県に生まれ、6歳で被爆した漫画家、中沢啓治が、自らの体験を赤裸々に綴った同名漫画のアニメ映画化作品。1945年8月6日、広島県広島市に住む少年、中岡元は米国軍により投下された原爆により、父親や兄弟を失う。自らも原爆症の恐怖に苛まれ、身近な人々の死に苦しみながらも、元はたくましく戦後の混乱期を生き抜いていく。
監督: 真崎守
声の出演: 宮崎一成、甲田将樹、井上孝雄ほか
「菊次郎の夏」
 母親探しの旅に出る少年と、ひょんなことから少年と行動をともにすることになった中年男性の道程を描いた北野武監督・脚本・主演のロード・ムービー。父親を亡くし、母親と離れて暮らす小学3年生の正男は、母親に一目会いたいと家を飛び出す。そんな正男を心配した近所のおばさんは、夫の菊次郎を同行させるのだが......。
母親探しの旅に出る少年と、ひょんなことから少年と行動をともにすることになった中年男性の道程を描いた北野武監督・脚本・主演のロード・ムービー。父親を亡くし、母親と離れて暮らす小学3年生の正男は、母親に一目会いたいと家を飛び出す。そんな正男を心配した近所のおばさんは、夫の菊次郎を同行させるのだが......。
監督: 北野武
出演: 北野武、関口雄介、岸本加世子ほか
「おくりびと」
 納棺師という馴染みの薄い職業に目を向けた青木新門著「納棺夫日記」を基にした人間ドラマ。第81回アカデミー賞外国語映画賞を受賞し、国内外で注目された。プロの音楽家として活動していた男が、音楽の夢を諦めて帰郷。「旅のお手伝い」といううたい文句に惹かれて入社した会社で、死者を棺に納めるまでの準備を整える、納棺師という仕事に就く。
納棺師という馴染みの薄い職業に目を向けた青木新門著「納棺夫日記」を基にした人間ドラマ。第81回アカデミー賞外国語映画賞を受賞し、国内外で注目された。プロの音楽家として活動していた男が、音楽の夢を諦めて帰郷。「旅のお手伝い」といううたい文句に惹かれて入社した会社で、死者を棺に納めるまでの準備を整える、納棺師という仕事に就く。
監督: 滝田洋二郎
出演: 本木雅弘、広末涼子、山崎努ほか
![]()
4月15日(水)
| 15:00 | 「The Influence of Japanese Art on Western Artists」 (レクチャー) ジェームズ・マルパス氏(サザビーズ・インスティチュート) |
| 16.00 | 「Portrait of the Artistic Genius Katsushika Hokusai」 (ドキュメンタリー) |
| 入場料 | 無料 |
4月16日(木)
| 12:30 | 「はだしのゲン」 |
| 15:00 | 「筆子・その愛―天使のピアノ―」 |
| 16:45 | 山田火砂子監督トーク・イベント |
4月17日(金)
| 13:30 | 「菊次郎の夏」 |
| 17:30 | 「おくりびと」 |
| 入場料 | 5ポンド(高齢者4ポンド、子供1ポンド、 一作品につき) |
| 場所 | The National Gallery (Sainsbury Wing Theatre, Sainsbury Wing) Trafalgar Square London WC2N 5DN |
| チケット | 下記ウェブサイト、または当日劇場で 上映30分前から(現金、小切手) |
| ウェブ | www.nationalgallery.org.uk/what/film |



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?