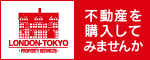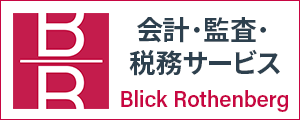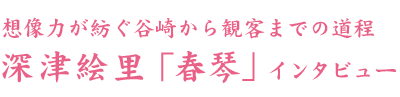
1月22日、東京のホテル・ニューオータニ。日本の演劇界では権威ある賞として知られる紀伊国屋演劇賞の栄えある贈呈式の席に、個人賞を受賞した一人の女優の姿はなかった。そのとき、彼女はロンドンにいた。個人賞を受賞した作品、谷崎潤一郎原作「春琴」の再演となるロンドン公演に向けて、汗を流しながら稽古に励む毎日。初日を間近に控え、連日、朝から晩までスタジオに篭り切りだというその人、深津絵里に話を聞いた。(取材・文: 本誌編集部 村上 祥子)
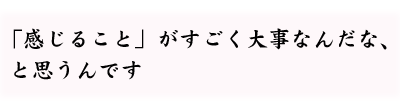
ロンドンでの「すてきな」日々
「なんつう心得違いしてんのや!」
稽古場の外でインタビューが始まるのを待つ耳に、同じ言葉が何度も、何度も繰り返し聞こえてきた。複数の男女の声が重なり合うなか、ひときわ凛と響く声がする。ピンと張り詰めた、でも不思議と耳障りの良い女性の声音──演技派として日本では知らぬ人のない人気女優、深津絵里の声だった。
1月中旬、ロンドン南部ウォータールー。深津が「春琴」の稽古を重ねる小さなスタジオから、近くのコーヒー・ショップへとインタビュー場所を変えるその道すがら。シンプルな黒い服に身を包み、足取りも軽く外を闊歩する深津は、オレンジ色の街灯がレンガ造りの建物を照らすロンドンの街並みにしっくりと馴染んでいる。
渡英したのが1月5日。慣れぬ異国生活で苦労しているのではと思い、約2週間のロンドン生活の印象を聞いたところ、「食事は美味しいですね。食材、特に野菜が新鮮だなって思います」という一言が深津の口から飛び出した。ロンドン在住 者としては意外とも思えるその言葉。聞けば稽古場近くにあるバラ・マーケットで、ヨーロッパ各地から集まる食材を仕入れては、皆で自炊を楽しんでいるのだという。テレビや舞台で見るがままの、意志的で黒目がちな瞳を輝かせ、ロンドンでの日々を語る深津。連日の長時間に及ぶ稽古で、心身ともに疲れていると思う、と言う英国人制作者たちの心配をよそに、サイモン・マクバーニーとの共同作業の「すてきさ」を語る彼女の声はあくまで軽やかで柔らかい。
「戯曲どころか、お芝居の筋すらなかった」
季節の移ろいを感じ、言葉にされずとも相手の気持ちをくみ取り、幽玄の美を慈しむ − 日本人は、感覚では何となく掴めるけれども、はっきりとは説明できないものを尊ぶ情緒的な国民だと言われる。そんな抽象的であいまいな日本的概念を、何と英国人が舞台化するという。そんな不可能とも思える難事に挑戦するのは、サイモン・マクバーニー。リアリズムを徹底し、すべての動きやセリフに意味を求める傾向の強い英国演劇界にあって、映像や照明を駆使し、身体性、視覚性を追求する独自のスタンスで知られる演出家だ。
選んだ題材は、昭和を生きた文豪、谷崎潤一郎。美しく気位の高い盲目の女性、春琴と、奉公人で内縁の夫でもある佐助の愛の形を描いた短編小説「春琴抄」のストーリーに、陰翳(いんえい)、闇の中にこそ美があると日本独自の美意識を説く随筆「陰翳礼讃」の概念を織り込んだ作品であるという。そしてその作品の核となる春琴を演じるのが、深津絵里、その人である。
深津が「春琴」に出会ったのは、今から2年前の夏のこと。サイモン・マクバーニーが日本で行ったワークショップに招かれたことが、そもそものきっかけだった。
「この『春琴抄』を舞台にしたいという構想は、サイモンさんの頭の中に10年以上、あったそうです。そのために何度も日本でワークショップを開催されていたみたいなんですけれど、そのときには結局、村上春樹さんの『エレファント・バニッシュ』を先に制作されることになって。でもどうしてもこの本を舞台化したいということで、2年前の夏頃だったかな……、春琴のワークショップに声をかけていただいたんです」。
サイモン・マクバーニーは1995年、初来日した際に英語版の「陰翳礼賛」の存在を知り、その魅力にとりつかれたという。そして2008年、その10年来の思いを一つの形に昇華させた。サイモン・マクバーニー率いるコンプリシテと、東京の世田谷パブリックシアターの共同制作による「春琴」上演。10年という莫大な時間のなかで、具体的にはどのように作業が進められたのだろうか。
「まずは『春琴抄』と『陰翳礼讃』という2つの作品がサイモンさんの頭の中にあって。あとはそれを何とかしたいという彼の『思い』と、こちらが受け止める『理解力』、それだけですね」。「それだけ」と軽く言いながらも、深津の口調には切実な響きが込められていて、その作業が並々ならぬものであったことをうかがわせる。
「日本だと先に戯曲があって、その後で役者さんが決まって……というパターンなんですが、サイモンさんの場合は、全く何もないところから始まるんです」。驚いたことに、戯曲どころか、芝居の筋になるものすらなかったという。あったのは、谷崎の2冊の本、そしてサイモン・マクバーニーの頭の中にある構想のみ。
「だからものすごく時間がかかりました。サイモンさんが小説の1シーンをピックアップしてきて、みんなはどう思うか、って話し合ったり。それで気になる言葉をグループに分かれて、体で表現してみるという繰り返しを延々と続けていったんです。どこから始めるか、とか、何が大事か、というのは全く決まっていなくて。サイモンさんの頭の中にはあるはずなんですが(笑)。みんなは色々な想像力を使って、それに近づいていくという作業でした」。
ワークショップで選ばれた役者たちは皆、自分が何の役柄を演じることになるのかも分からぬまま、稽古を続けたという。役者のなかには、与えられた人物像を掘り下げて、掘り下げて、自分なりの役柄をつくり上げるという手法を好む人も多いだろう。演技派として知られる深津としては、やりづらくはなかったのだろうか。
「どうなんだろう……、そういうやり方もとてもいいと思うし、これまではそれしかやってこなかったんですけれども、それだけに余計、こういうつくり方が新鮮で面白かったんですよね。自分がどんなものになってもいいんだっていう自由さ。それはこの作品を客観的に見ることにつながるし、一つの役だけにのめり込まずに、色々な役の解釈を把握できて、本当に面白い経験でした」。
これまでの女優としての長年のキャリアとは全く異なるアプローチ。しかし口の端に笑みを浮かべながらゆっくり語る深津の顔には、楽しくて仕方がないという表情が見え隠れする。日本だと稽古に費やす時間は1カ月ほど。対して今回は3カ月。「サイモンさんの演出は細かく細かく掘り下げて、丁寧に丁寧につくっていく日本ではなかなかない演出方法で、本当に贅沢な時間だなあ、って思いましたね」という言葉に、舞台女優、深津絵里としての顔が見えた。

Photo: Tsukasa Aoki 「春琴」初演より
抽象的思考を具象化する究極の作業
あるときは春琴に奉公していたという女性から、またあるときは「鵙屋(もずや)春琴伝」という小冊子からの引用というように、さまざまな語り口を用いて、読者が一つの像を結ばないよう物事を故意にぼかす作風、句読点を極力排除した独特な文体。第二次大戦下を生きた谷崎が、古き良き時代の日本を懐かしみ、つくり上げた「春琴抄」は、現代に住む我々日本人にとっても難解な文学作品だ。果たして英国人に、そうした日本人の感覚を真に理解することができるのか。どうしても、そんな穿った思いがよぎってしまう。日本人にとっても難しい、という言葉に、「そうですね。読めない漢字も出てくるし」とさらりと笑った深津は、ロンドン公演ということでサイモン・マクバーニーが特に意識したという点を次のように語ってくれた。
「日本人ならば何も言わなくても感じられることを、あえて見せることで分かってもらう、といったようにしている部分はかなりあると思います」。例えば劇中、「卒塔婆(そとば)」という言葉が出てくるが、それは「日本人だったら、すごく若くさえなければ(笑)、何となくでも理解できる」が、こちらでやる場合には、その言葉が何を示しているのかを、しっかりと台詞で説明するという。そうしたちょっとした疑問への答えを提示していく作業は、かなり意識的に行っているようだ。とはいえ、言葉では説明できない、日本人が「何となく」感じる部分を理解するというのは、やはり別の困難さを伴うのではないだろうか。
「現在の日本人が『陰翳礼賛』を読んだとしても、分かる人と分からない人がいると思うんですよね。ろうそくがつくる灯りと闇と言っても、ろうそくで暮らしていたことすら、私たちにとってはもはや想像でしかない。それをどこまで理解できるのか。日本人だからはっきり理解できるとも言いきれないですよね。そこが面白いなって思ったんです。日本人だから分かるっていう本じゃない。それをサイモンさんがやるから意味がある、面白いんだろうなって」。静かに微笑みながら、あっさりと言う。しかしこの言葉は、深津とサイモン・マクバーニーが長い月日をかけてともに一つの作品を築き上げてきた信頼の上で発せられた、重みを持っている。演出される側として、そんなのは日本じゃない、と納得できない部分はあったか、と問うと、「そう感じる瞬間が多少はあったとしても」と前置きした上で、こう続けた。
「サイモンさんは自分だけの考えでこう、と決めつけることは絶対にないんです。自分は英語で読むととても面白いけれども、日本語で読むとどうかっていうことを細かく聞いてきてくれる。日本の作品だということを常に尊重してくれていて、私たち日本人の意見として「それは美しくない」とか「それは理解できる」みたいな考えをすべて平等に扱ってくれるんですね。だからつくっていて、自分の意見を持つことができるんです」。
今回のインタビュー中、深津は何度も「サイモンさんの頭の中にある」という言葉を繰り返した。構想10年。幾度も原作を読み返し、独自の世界を頭のなかで構築する一方で、日本人が持つ「感覚」を尊重し、役者との対話で生まれた瞬間を捉えていく。そうした作業を、深津ら信頼できる仲間と徹底して行うことで、サイモン・マクバーニーは、日本の抽象的思考を具象化するという、究極の作業を完成させていったのだろう。

Photo: Tsukasa Aoki 「春琴」初演より
想像力を使って「感じる」
サイモン・マクバーニーは2003年、村上春樹の短編「象の消滅」ほか3編を基にした舞台、「エレファント・バニッシュ」を制作。映像や照明を使い、村上春樹の精神世界を見事に可視化したと話題を呼んだ。そして今回の「春琴」では、人形を含め、複数の人間が春琴その他の役柄を演じることで、さまざまな視点から語られる春琴像を多角的に描いていく。はっきりとした主義主張があるわけでも、明解な起承転結があるわけでもない。そんな抽象的な題材をあえて選び、物語の持つ空気感を視覚的にはめ変えていく。そうした過程を経て創造されたサイモン・マクバーニーの世界は、斬新であると同時に、何を訴えているのかと、時に観客を戸惑わせることもある。今回の「春琴」で、果たして観客は舞台上に何を見ることにな るのだろうか。
「谷崎という人は誰で、佐助という人は誰なのか。佐助とは、実は谷崎なのか、佐助が『鵙屋春琴伝』を書いているのか、そうじゃないのか。『春琴抄』のストーリーの隙間に谷崎自身の影が見え隠れしているところを感じる、この本を読んでいて面白いのは、そういう匂いなんです」。はっきりとした筋や主張が見えるわけではない。しかしそこにほのかに漂う「匂い」を感じる̶̶谷崎の「春琴抄」を読んで深津が感じたこの「匂い」こそ、観客が舞台上で見ることになるサイモン・マクバーニーの描く「春琴」の世界を知る鍵となりそうだ。
「最後は、佐助が取った行為をどういう風に思いますかっていう問い掛けで終わっている本なんですね。それは舞台の方でも、どう感じるのかっていうことで終わっているんですけれども。だから観て、即座に『私はこう思う』っていう答えが出る作品ではないんだろうなって。感じるっていうことが大切な作品なのかな、というのを演じながら思うんです。春琴にしても、盲目で、ものを見ることができないからこそ、手に触れるものへの感覚が鋭かったり、嗅覚や聴覚が研ぎ澄まされている。この作品ではそういう『感じること』がすごく大事なんだなと思いますね」。
サイモン・マクバーニーが谷崎の本を読んで感じた「何か」を、深津ら出演者たちが想像力を使って理解し、その役者が可視化した世界に漂う「匂い」を、今度は観客が想像力を使って感じる。「春琴」における、谷崎から観客に至るまでの長い道程に関わる人々は、英国人であれ日本人であれ、役者であれ観客であれ、誰もが想像力をもって目や耳に示される以外の存在を、感じ取ることが要求されるのだ。
映画やテレビに大活躍していた深津が、舞台の道に本格的に進んだのは25歳のとき。「舞台はいいよ」と何度も聞かされ て、「どう面白いのかを自分でちゃんと知りたい」と思い、日本演劇を牽引する人気演出家、野田秀樹の「キル」再演に出演したのがきっかけだった。「自分には『知りたい』という欲がすごくある」という深津。知りたいという気持ち、好奇心が自分を導いているのかも知れない、と言う彼女が今回、この「春琴」という未知なる世界に魅せられたのは、当然のことだったのかもしれない。思いのほか長くなったインタビューを終え、コーヒー・ショップから駅に向かう深津の足取りはやはり軽やかで、その足音は、明日も朝から夜まで続くという稽古で未知なる瞬間に出会うことが待ちきれないと物語っているかのようだった。
深津絵里プロフィール
1973年1月11日生まれ。映画やテレビ、舞台と、フィールドを問わず活躍する、若手演技派女優。数々の連続テレビ・ドラマで主演を務める一方、映画分野では2004年、森田芳光監督作品「阿修羅のごとく」の演技により、第27回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。舞台にも積極的に出演しており、野田秀樹や蜷川幸雄など、日本を代表する演出家の作品の数々に出演している。
あらすじ
薬種商の娘、春琴は、9歳の時に失明。以来、音曲を本格的に学ぶようになる。春琴の付き添い人として仕えていた佐助も、やがて弟子として春琴から三味線を学ぶようになり、2人の関係はより一層密接したものとなっていった。音曲の師匠として佐助とともに暮らす春琴はある日、その美貌と高慢さゆえに、自らの顔をひどく傷つけられる憂き目に遭う。そして佐助はそんな春琴を見て、とある決心をするのであった。
Shun-kin
1月30日〜2月21日 19:45
(2月14日、2月21日は14:30、19:45)
料金: 10〜40ポンド
Barbican Theatre
Silk Street, London EC2Y 8DS
Box Office: 0845 120 7550
*日本語公演(英語字幕付き)



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?