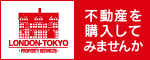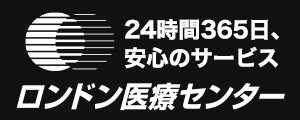醤油を世界に広める
醤油を世界に広める「正田醤油」の英国法人社長
正田敏郎さん
[ 後編 ]かつて「醤油らしきもの」を作っていたウェールズの工場の建て替えから始まり、英国各地のスーパーマーケットに製品を納める日本企業に生まれ変わるまでにはどのような過程があったのか。英国法人の社長自らが「そんなに敷居が高い会社ではない」という正田醤油が英国で成功した理由とは。全2回の後編。
![]()
しょうだとしお - 1963年8月21日生まれ、群馬県出身。学習院大学法学部法学科卒。1873年創業の老舗である正田醤油株式会社の創業家に生まれる。日本の商社の駐在員として米国やオランダへの赴任を経験した後、正田醤油が英国に海外初となる工場を設置したのを機に同社に入社。2000年に同社の英国法人となるショウダ・ソーシーズ・ヨーロッパのマネージング・ダイレクターに就任した。同社では、ウェールズの工場で現地の水を使って製造した醤油やそのほか各種ソースを主に英国内の大手スーパーマーケットで販売される食品用に供給している。
www.shodasauceseu.com
押し付けても受け入れてもらえない
刺身、丼もの、冷奴からおひたしまで。今や英国のスーパーマーケットやテイクアウェイ店で入手できない日本食などないと言えるほどまでに日本の食文化は浸透した。器用に箸を操る英国人も、もはや決して珍しい存在ではない。
一方で、在英邦人の間では、英国で浸透している「日本食」に多少の違和感を覚える向きもあるかもしれない。カリフォルニア・ロールに代表されるユニークな巻き寿司や、シャリまで醤油にどっぷりと浸してしまう握り寿司の食べ方を見て眉をひそめた経験のある日本人は少なくないはずだ。醤油という日本の伝統の味を長らく受け継いできた正田醤油の日本人社員は、こうした光景を目にして歯がゆい思いを抱いたことはないのだろうか。

ウェールズの工場では顧客の要望に応じたソース作りを行う
「うちはそんなに敷居が高い会社ではないので」と苦笑しながら話す正田社長は、この点でかなり柔軟な考えを持っている。「『これが本来の日本食文化ですよ』と押し付けたところで、英国人にそのまま受け入れてもらうというのは難しいでしょう。英国ではむしろ各スーパーの食品棚を観察するなどして、彼らの好みがどんなものであるかを学ぶことの方が大事だと思います」。
例えば、「減塩に関する各スーパーの規制への対応」と「見た目に分かりやすい日本食らしさの実現」という考えを背景にして生まれた「塩分は抑えつつも料理の色づけがしやすい色の濃い醤油」への需要が英国にはある。日本国内では恐らく特殊と捉えられるであろうこうした要望にも、正田醤油は真っ直ぐに応えてきた。また製造する商品は醤油や大豆を用いたものに限らず、「こんな感じのものは作れますか」との問い合わせが寄せられれば、「ソースであればどんなものでも」と請け負う。誇るべきは日本食のあるべき姿ではなく、商品の開発力なのだ。
「我々も英国のお客様に向けて、日本の醤油とはこういうものなのですよ、というプレゼンテーション資料を見せたりはします。ただその後には『まあ、あまりこだわらないでください』とも言い足しますね。そして『お互いに協力してやっていきましょう』というスタンスで仕事を進めていきます」。
こだわりは商品開発力とそのスピード
正田醤油では、顧客の要望を汲み取り、そして製品として具現化するための様々な仕組みを用意している。例えば、同社には醤油の異なる色を示したカラー・チャートがある。真っ黒から灰色に近い色までのグラデーションを示すこのチャートの各段階には色番号が振られており、発注側は「①と②の中間の色でお願いします」といった形でサンプルの製造を依頼することができるのだ。
その際に重要なのが、サンプルを用意するまでのスピード。「我々のお客様の多くが、醤油やソースを味付けに使うレディー・ミールの製造元です。彼らはスーパーから「何日までに新しい商品の提案を出してください」という締め切りを設定されています。だからサンプルを迅速に送ると、製造元から重宝がられるんですよ」。そうした努力を10年以上も根気強く続けてきたからこそ、事業を軌道に乗せることができたのだという。「だからサンプルを送るまでのスピードに関しては、かなり厳しく管理しています。そういう点では『日本的な対応』を取っていると言えるかもしれません」。

英国の各スーパーにはたくさんのレディー・ミールが並ぶ
つまりは自分らしさを理解してもらうために他者が存在するのではなく、他者を喜ばすための手段となることで自分らしさが輝き始める。正田醤油の成功例には、海外で事業を営む日系企業にとってのヒントが隠れているのではないだろうか。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?