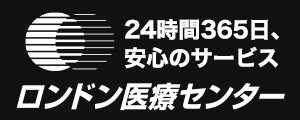最小不幸社会と第三の道
菅首相は、「最小不幸社会」を唱えている。市場原理主義と公共事業頼みのいずれでもないという立場から、「第三の道」とも言っている。彼は、英国のブレア元首相の政治手法を熱心に研究していた。
当地では、労働党が下野し、そのブレア体制が一段落した。これから、ブレア氏の行った「第三の道」への評価が歴史的な意味でなされる。ロンドン大学のギデンズ教授らが提唱したこの思想は、サッチャー流の自由主義が掲げる小さな政府ではなく、サッチャー以前の労働党のような何でも国有化する社会主義でもない、「第三の道」を説く。人間の生存に関わる事項や社会的弱者の経済状態などの改善には、社会民主的に政府が積極的に関与する一方、それ以外の分野では、企業、更には市民やNPOとも連帯して社会資本の整備に努めるという考え方だ。具体的には、病院事業、NHS改革が実践された。菅首相は、今後下される、本家英国のブレア評価の影響を受けるだろう。
ブレア氏の第三の道は、あまり評価されていない。その理由は、降板後の英国経済不調の責任である。この欄で何回も書いたように、経済好調はブレアの政策のおかげというよりも、北海油田の恩恵、サッチャー政権の緊縮財政でできた財政の余裕、ユーロは導入せずに金融政策の自由度を保ったサッチャーの判断によるところが大きく、そして何よりも、共産主義崩壊の結果によるグローバリゼーションの下でのロンドンの金融都市としての地位向上のおかげである。
第三の道の中身であるNHS改革、国有企業の民営化、教育改革は、いずれも成果は明確ではない。国有企業の民営化も海外売却を進めただけであり、売るだけなら誰でもできる。結局、公共部門や準公共部門で働く人のサービス向上への意識改革はまだ十分ではない。またブレアについては、金融分野の規制緩和による金融業の肥大化と、製造業の著しい縮小への批判が強い。金融バブルの崩壊を予防できず、肥大化した金融の痛みが、経済全体の痛みとなり、他の産業による回復が困難となったこと、国有企業売却で政府にはもはや売るものがないことなどが厳しく問われ、労働党は敗北した。本来は公務員の意識改革も含め息の長い話である第三の道が、財政余力の食いつぶしと経済変動で道半ばとなった感がある。
第三の道の生煮え度
ギデンズの「The Third Way」を読むと、抽象的な考え方は分かるが、HOWというところはあまり詳しく書いていない。学者の限界と言うべきだろう。民間が市場を通じては供給できないもの、政府が自ら投資、運営すべき事業は何か、どこまで政府が関与すべきかなど、具体論になると急に難しくなる。人間の生存に関わる問題になるのは、医療介護、教育、その他生活に必要な社会インフラ(交通、電気ガス水道等)である。これらについて、政府はどこまで金と口を出すべきなのか。
米国の政治哲学者ロールズは、格差原理(最も状態の悪い人の改善になる施策であれば正義に叶う)を示しているが、第三の道では、そういう議論も十分でない。人間の生存に関わる事項や社会的弱者の経済状態などの改善に政府は積極的に関与する、と言うだけである。加えて、経済変動に対する財政の処方について、ケインズ流積極財政か、自由主義流の放任・最小介入かについても明確でなく、結局市場の信認維持のために、銀行を一つも潰せず、現実の前に成す術がない。リスク耐性の議論が欠如している。
「最小不幸社会」は、「第三の道」以上に曖昧な概念だ。日本の民主党政権でなされたことは、国労との和解、肝炎訴訟の和解、年越し派遣村への便宜供与など、社会的な弱者への救済促進が目立つ。しかし、いずれも税金で負担するものである。
話題を集めた「事業仕分け」も、実は大変なことをしているという謙虚さ、惧(おそれ)が感じられない。ある行為の社会的意味の詳細な検討・分析は容易な作業ではない。結局、具体的な問題について、想像力を持った具体的な解決とその説明がない中でのスローガン政治は、声の強いものが勝つという腐敗を生む。
リスク耐性はどうか。英国の金融業は、日本では製造業である。まだまだ力があるが、海外志向を強めており、中国バブル崩壊へのリスク耐性は著しく弱まっている。新興国需要を取り込むことにはリスクも伴う。韓国経済のアップ・アンド・ダウンは他山の石である。地道な作業なきパフォーマンスやスローガンのみでリスク耐性を考えない政治、安易な消費税増税の検討開始では、政権は危ういといわざるを得ない。次回はブレア外交の対米依拠と民主党の中国傾斜を比較してみる。
(2010年6月6日脱稿)
| < 前 | 次 > |
|---|

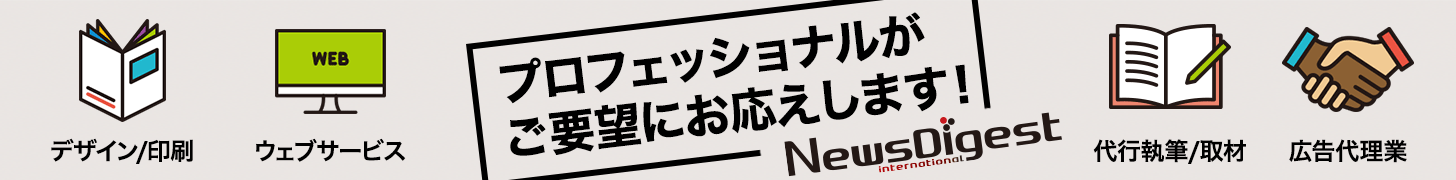

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?