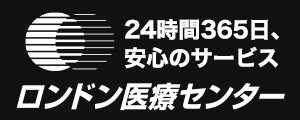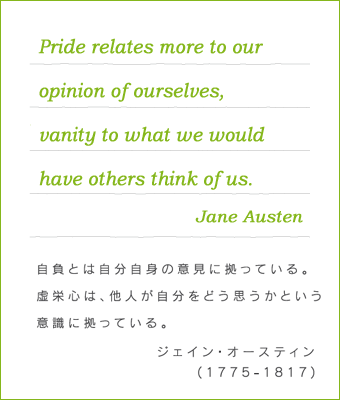
オースティンが残した小説のなかでも最高傑作の呼び声が高い作品、「Pride and Prejudice(「自負と偏見」)」のなかの一節である。作品のタイトルにその言葉をすえたくらいだから、さすがにオースティンの「自負」を語る切れ味は鋭く、そこにユーモアも生じ、また21世紀の現代にまで通ずる永遠なる叡智も生まれたのだった。
今回の言葉の前には、自負と虚栄心は別物ながら世の人々はしばしば混同しているとの弁が置かれ、両者の差を展開してみせたのがこの言葉という訳だ。確かに、人は他人の目を気にしているものである。自分の行い―仕事にしろ生き方にしろ、自負=誇りを持つといっても、実は純粋に自己の充足に終始する人など稀で、多くは他人の目や評価、賞賛などをどこかで待ち望んでいる。「誇りを持て」などとよく言われ、当人もその気になって胸を張っているが、実際のところ、どれほどが他人の眼差しを離れ、「虚栄心」を免れ得ているか、大いに疑問だ。
ひどい場合には、他人の目があってこそ誇らしき行いもあり得るという場合すらあって、他人の眼差しが目的化してしまっている。政治家の語る「誇り」などは、多くのケースがこの手合いである。そこまで露骨でなくとも、知らず知らずのうちに他人の視線が気になりだし、いつしかすっかりその罠に嵌まってしまうというケースは、かなりの確率になりそうだ。そう思っておのれの胸に問えば、潜在化していた他者からの眼差しへの意識を、悟ることになる人も多いことだろう。
真の自負、誇りならば、他人の視線など関係がない。そして、そのような誇りは、空しさとは無縁だ。だが、他人の視線に拠ってたつ「虚栄心(vanity)」は、言葉そのものにも「虚(vain)」がつきまとうことで明らかなように、空しさを影として抱える。だから、その手の「誇り」は脆い。他人の目が冷ややかになったり、こちらを向かなくなったりするというと、ちゃんとした自前の骨でなかった分、ぽきりと折れ崩れて、手痛い挫折を余儀なくされる。
オースティンの主張は明白だ。人は、虚栄心を捨てて、真の誇りに生きるべし!
本来、自負とは、地道なおのれ磨きの結果である。他人の目など気にせずに自己を磨き上げ、内側からおのずと輝き出すものである。そのようにして、他人の視線に頓着せず、おのれを磨いた人は、他人の目に惑わされてあくせくした虚栄心の輩に較べて、その実、他人の目からしても、輝きが違ってくるのである。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?