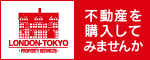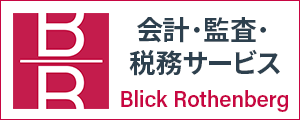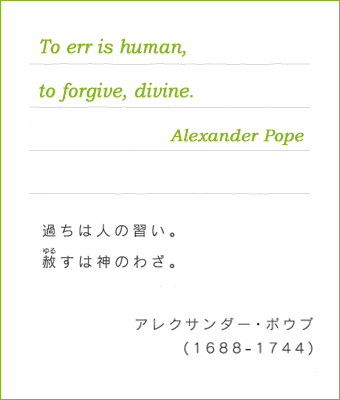
かれこれ30年前になるだろうか、佐木隆三氏の「復讐するは我にあり」というノンフィクション小説が直木賞をとり、映画化もされて、大いに話題となったことがあった。このタイトルは、新約聖書「ローマ人への手紙」のなかの「汝、復讐するなかれ。復讐するは我(神の手)にあり」を下敷きにしたものだが、主人公の連続殺人犯がクリスチャンの家出身であるところがミソで、神をも恐れぬ冷血の凶行は、聖書の教えを逆手にとるかのように、人間への「復讐」を自身の手で行なった不可思議なリアリティを生んだのだった。
さて、「復讐」が神のわざであると同様、「赦し」もまた、人の手を超えたものだとポウプは言う。18世紀を代表する古典主義の哲学詩人の目には、神と人の間には不可侵の境界線が存在したのだろう。人生は試行錯誤の連続。赦すという絶対の愛は、神のみのなせるわざ。人は神の領域に踏み込むような驕りを捨て、分をわきまえ、つつましく生きよと、ポウプの主張を噛み砕いて語れば、そんなところに違いない。人は無軌道でも仕方ないと、決して放縦を容認したものではないのである。
面白いことに、仏教の浄土真宗の教えのなかには「他力本願」という考えがある。親鸞は「他力というは如来の本願力なり」として、衆生の魂の救済は阿弥陀仏が本然的に持つ願いだとした。故に、「悪人なおもて往生をとぐ」と、あらゆる人間の「往生」=救済は、弥陀の本願にすがりさえすればあまねく約されたものだと説いた。
こうした「他力」の哲学は、今回のポウプの言葉と、どこか相似形(そうじけい)を描く。もちろん、仏の慈悲とキリスト教の愛の世界は、正確には差を持つであろうが、人の上に絶対なる世界を規定した両者の考え方を、私はとても興味深く思う。人智の及ばぬ絶対なるものを崇めることは、人を穏やかにし、ややもすれば生き馬の目を抜く式の蛮性や攻撃性を発揮しかねない人間の業を抑えることになる。
ただ、そう承知した上で、私はなおも思う。人の心に宿る愛の本質のなかには、赦しという概念が含まれる。イタリアオペラのような愛憎劇も人間の業のうちだが、対立や嫌悪、憎しみを超えて、時に人は大いなる澄んだ愛に目覚める。それは、人が生きる上で立ち現れる最も崇高な感情に違いない。神のわざを人が我が手にしようとした時、「復讐」であれば、まっ逆さまに地獄へ堕ちるしかない。だが赦しの愛であれば、人は限りなく神聖さに近づく。「forgiveness」は、人が求めるべきもっとも至高の徳だと、ポウプは「divine」という言葉を使って、そう言いたかったのかもしれない。
| < 前 | 次 > |
|---|

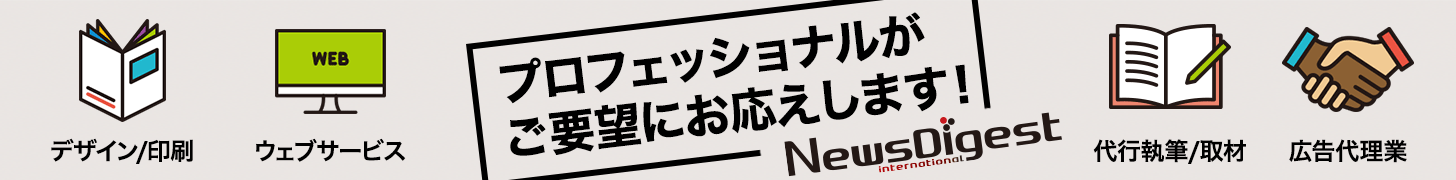

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?