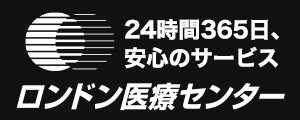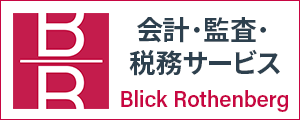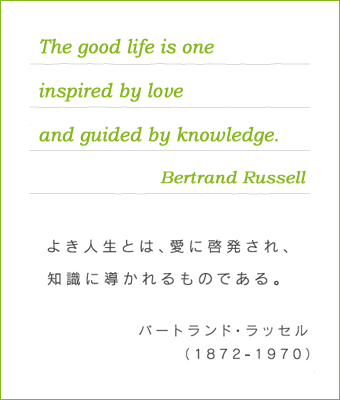
知と情という。このふたつがバランスよく両立すれば、人生は至福のものとなろう。愛と知に恵まれた人生は、満ち足りたものに映る。もっとも、ラッセルのこの言葉は、一見するとあまりにも当たり前すぎて、いささか凡庸な感じがしないでもない。結婚式のスピーチに、名言集から引用するのをパターンとする人がいるが、そういう人なら、迷うことなく飛びつくに違いない。そして、披露宴さえ終われば、記憶の引き出しの奥にでも仕舞れて、次の出番が回ってくるまで、顧みられることもないであろう。そういう無難な人生訓として、この言葉と付き合うことも確かに可能なのである。
だが、もう一度、目を見開いて、ラッセルの言葉と向き合っていただきたい。「愛に啓発され」とあり、「知識に導かれる」とある。愛と知がありさえすれば事足りるのではない。それぞれに、かなりの磨きをかけたものが要求されている。語られた言葉は簡潔だが、望ましき人生を希求する真剣さは、道を求めるほどに激しいのである。
愛に啓発される、インスピレーションを受けるとは、どのようなことなのだろう。ただ肩を寄せ合い、ともに日々を重ねるのとはわけが違う。趣味が合う、一緒にいて肩が凝らないと、そのような程度では生ぬるい。常に互いの存在が相手を触発し、思想にも感性にも行動にも、飛翔の翼を与える泉とならなければいけないのである。愛がよほど真剣で、妥協や惰性を撥ねのける一途さに貫かれていなければ、このような新鮮な輝きに満ちた至上の愛は成立しない。
知もまた然(しか)り。人生を導くような知識は、単なる情報の詰め込みとは違う。道を開くに足る知識を得るには、相当の覚悟が必要となる。愛にも知にも、真剣勝負以外はあり得ない。
ラッセルは、生涯に4度の結婚をした。それも、啓発し啓発される真実の愛を模索し続けた結果だろう。真実を求めれば、過激にならざるを得ない。波風を避け、無難に人生を送ることをよしとするようなら、ラッセル流の真実に近づくことはできない。
1967年、死の3年前に出た「自伝」のなかで、ラッセルは、自分の人生を支配してきたのは、シンプルながら圧倒的に強い3つの情熱であると言っている。すなわち、愛への希求、知への探求、そして人類が受けている辛苦への耐え難い同情心であるとーー。
数学者にして哲学者、20世紀のイギリスを代表する知の巨人が、個人的にも社会的にも、生きることに真剣で、火のような理想を抱えて道を求めてやまなかったことに、私は胸を熱くせざるを得ないのである。
| < 前 | 次 > |
|---|

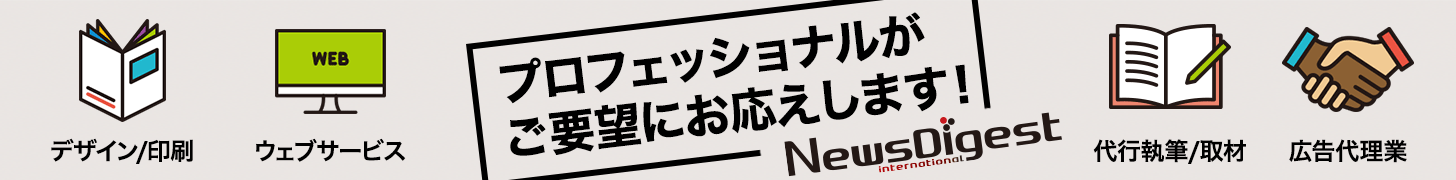

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?