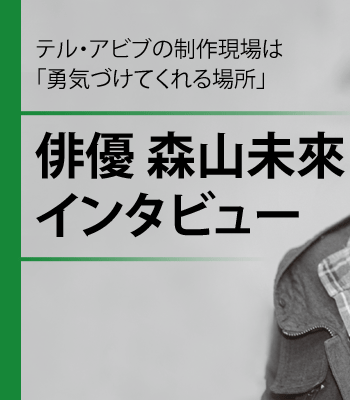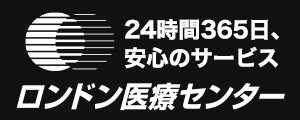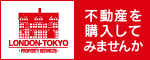ロンドンにあるコンテンポラリー・アート・ギャラリーICAで行われた国際交流基金主催の巡回日本映画上映会。その会場に、俳優の森山未來がいた。「モテキ」と「苦役列車」という2本の主演作品の上映に合わせ来英した森山は、現在、文化庁の文化交流使としてイスラエルに拠点を置き、活動している。イスラエルの大都市、テル・アビブでダンサーとして、また一人の人間として何を思い、日々を過ごしているのか、聞いた。
森山 未來 Mirai Moriyama
1984年、兵庫県神戸市生まれ。幼いころからジャズ・ダンス、タップ・ダンス、クラシック・バレエ、ヒップホップなどのダンスを始める。1999年、宮本亜門演出「ボーイズ・タイム」で本格デビュー。その後、テレビ・ドラマ「さよなら小津先生」「ウォーターボーイズ」などの話題作に相次いで出演する。2004年、映画「世界の中心で、愛をさけぶ」で主人公サクの高校生時代を演じ、日本アカデミー賞優秀助演男優賞など映画賞の数々を獲得。近年では舞台、映画、ドラマとジャンルを超え、幅広い活躍をみせる。最近の出演作品に、ミュージカル「100万回生きたねこ」、NHK土曜ドラマ「夫婦善哉」、映画「人類資金」など。現在、平成25年度海外派遣型「文化交流使」としてイスラエルを拠点に活動中。
皆が対等な立場でモノをつくる過程
スクリーン上で、男が路上で痰を吐き、好きな女性の手の甲を舐めて嫌悪され、唯一の友人に取り縋(すが)り金を無心する――日本中が好景気に沸いたバブル期にあって、性犯罪者の父を持ち、日雇い労働で生計を立てる中卒の19歳、北町貫多の半生を描いた映画「苦役列車」では、貫多の劣等感と虚無的な怒りが様々な場面でこれでもかとばかりに描かれる。酒で顔をむくませ、白パンツ一丁で路上をよたよたと走る、そんな目を背けたくなるほどの醜さをさらけ出して貫多役を演じているのは、俳優、森山未來だ。
「苦役列車」上映の直前、長めの髪を無造作にひっつめ、ブーツに細身のパンツ、ゆったりとしたチェックのシャツに身を包んだ森山が、一つひとつの質問に滔々(とうとう)と答えていく。話しながらしきりに動く、しなやかな腕や指先。イスラエルに滞在しているという意識があるからかもしれないが、どことなく無国籍な空気を纏(まと)ったような、不思議な佇まいが印象的だ。
文化的国際交流の発展を目的として、文化庁が芸術家や文化人を一定期間、海外に派遣する文化交流使制度。昨年、この文化交流使に指名された森山が選んだ国は、イスラエルとベルギーだった。あまり一般的な選択肢ではないように思えるが、そこには個人レベルでのつながりがある。2011年に日本を含む世界各地で公演が行われた「テヅカ」、12年末から13年にかけて上演されたミュージカル「100万回生きたねこ」。この2作品に出演した森山は、前者の振付を手掛けたベルギー出身のシディ・ラルビ・シェルカウイと、後者の演出・振付・美術を担当したイスラエル出身のインバル・ピントとアブシャロム・ポラックとの制作過程に魅せられた。
「テヅカでは、漫画家の手塚治虫が描いた世界感と同時に、漫画や文字――例えば日本の文字は象形文字からきていて、絵から文字に流れていくという歴史があり、そこから漫画へとつながっていくわけですが――、といった要素をも表現していきました。その際、例えば筆の動きを体で表現できないか、ということになったときに、コレオグラファーとしてラルビがいるのだけれど、トップダウンでダンサーたちに押し付けるのではなく、君はどういう表現ができるかと求めてきて、僕たちはそれに応えるという過程を体験できたことがすごく大きかった。そしてインバルたちとのクリエーションにおいても同じような感覚で仕事ができたんですね。舞台をつくる中で、ダンサーという存在と、コレオグラファーや芸術監督、もしくは演出家という存在が皆、対等な立場で物事をぶつけ合えるという環境がすごくいいなと感じました」。

ICAで行われた巡回日本映画上映会のQ&Aセッションで
自分を「勇気づけてくれる場所」
森山の文化交流使としての生活は昨年10月、イスラエルの大都市、テル・アビブを拠点にするピントとポラックのダンス・カンパニーに籍を置き、彼らの作品制作にダンサーとして携わるという形で始まった。制作過程に興味を持ったとはいえ、文化環境の全く異なる世界に一人飛び込んでみて、違和感は覚えなかったのだろうか。「逆に健全だな、と思いますね」と迷うことなく答えた森山は、これまでの役者としてのあり方にこそ、少々の歯がゆさを感じていたようだ。
「今までも、10代のころから思うことはちゃんと言いたいと考えていたし、こういう風にした方が面白いという提案をしてきたつもりでした。でも自分の視野が狭かったりだとか、提示できる説得力が足りなかったりだとか、様々な問題で結果につながっていかなかった。それが『モテキ』や『苦役列車』を通して、少しずつかなっていったというか、バランスが取れてきたんです。大根監督(『モテキ』)や山下監督(『苦役列車』)と作っていくプロセスは、こう すれば面白いだろうなというイメージと自分が表現できることのバランスがある程度とれていたと思うし、それを大根さんも山下さんも受け入れてくれる環境があったということが重要だったなと思います。だから今、インバルのカンパニーでやっているあり方というのは、自分の中ではとても自然なんです」。
自身の役者としての成長が、こうした制作過程への適応能力とでも呼ぶべき素地を与えてくれた。しかしそれだけでなく、やはり海外で活動しているということが及ぼす影響が大きいとも感じている。創作現場であるなしに関わらず、日本では誰かが誰かに対し、集団の中で意見を言うことがあまり許される風潮にはない。「その中で意見をぶつけていくこともできると思うんですよ」、そう言う一方で、その姿勢を貫くむずかしさを静かに語る。「周りのそういう視線に耐えながら、気付かないふりをしながら、傷つきながら、でも俺は思うことを言っているんだからってやり続ける。柔らかい感情を保ち続けるのは難しいのではないかなと自分は思います」。決して声を張り上げているわけではないのに、関西独特の穏やかな抑揚に乗せて運ばれる言葉がすっと耳に届く。皆が自由に意見を言って、自由に同意して、拒否する、そんなテル・アビブの制作現場は、自然であると感じると同時に自分を「勇気づけてくれる」場でもある。こうした環境や、その中で活動している人間の気持ちをじっくりと観察して、日本に戻ったときには、特に舞台制作の場に還元したい、と考えている。

映画「モテキ」より。様々な女性に翻弄される藤本幸世役を
テレビ・ドラマに引き続き演じた森山未來(写真右)と、
幸世の会社の上司、唐木素子役の真木よう子(同左)
肉体的で刹那的なパフォーマンス
現在、森山が滞在しているイスラエルは、非常に特異な状況下に置かれている国だ。近隣諸国との国交は一部の例外を除き断絶しているのに加え、アラブ人が住むパレスチナ自治区との紛争は、今なお解決の兆しも見えない。そんな政情不安を抱える国にあって、森山の住む大都市、テル・アビブは、文化的中心地として知られ、治安も良いとされているが、日本はもとより、英国の日常生活ともかけ離れた一面を見ることも多い。「カンパニーの中にも兵役義務で軍隊に所属している子がいるんですよ。イスラエルの兵役は男性が3年、女性は2年。彼も大丈夫だとは言っているんですが、もしかしたらそのまま帰らぬ人になる可能性がないわけではない。兵役に就いている人間は、休みの日には私服を着ていてもいいけれど、拳銃は持って歩かなきゃいけないんです。バスの中でも、ショッピング・センターにも、私服で拳銃抱えてる人たちがいる。それが彼らの日常なんです。だから(生と死が)紙一重の中で生活しているって言ってしまえると思うんですよね」。
そんな環境下で生まれたイスラエルのパフォーマンスを「刹那的」だと感じるという。粗削りだけれども、理論や理屈を超えてしまったところにある舞台上のパフォーマーたちの肉体性。それは良い悪いではなく、イスラエルという国の持つパワーになっているのではないだろうか。そしてもう一つ、イスラエルという国が建国してからまだ70年も経っていない、非常に若い国ということも大きいのではと森山は考える。
「最初のころ、国はテル・アビブという場所を芸術の街にしようと、ゲリラ的に起こるパフォーマンスを放置し続けたそうなんです。だからすごく大きなものからアンダーグラウンドなものまで混沌としていて。それを認めたという最初のきっかけがすごく良かったんじゃないでしょうか。芸術とか表現というものが人の心を支えていた時代がきっとあったと思うんです。今も同様にしてあると思うんですけど。その流れが、世界的に知られるイスラエルのコンテンポラリー・ダンス・カンパニーであるバットシェパ舞踏団のダンスのような、肉体的で刹那的なパフォーマンスを生み出したのだと思います」。

映画「苦役列車」より。北町貫多を演じる森山未來(写真左)と、
貫多のたった一人の友人、日下部正二役の高良健吾(同右)
歪で生々しい美しさ
森山がイスラエルで籍を置くインバル・ピント&アブシャロム・ポラック・ダンス・カンパニーは、バットシェパ舞踏団に所属していたピントとポラックが独立して立ち上げたカンパニーだ。ダンス、という一言でくくることのできない、幻想的で、でも人間の生(せい)を強く感じさせる摩訶不思議なその世界感は、日本を含む世界各地でも高い人気を誇る。なぜ、森山は彼らのつくる作品に惹かれたのか。
「彼らの表現っていうのは、刹那であると同時にすごく『歪(いびつ)さ』を感じるんです。代表作の『オイスター』では、手がない人や、手と足がつながっている人たちが出てくる。サーカス、それも煌びやかなのじゃなくて、かつて社会不適合者とされた人たちが国から援助されていない状況で、生きていく術(すべ)として日本の寺にあった見世物小屋のような感覚のものをつくっているんですね」。これは僕の勝手な妄想なんですけれど、と前置きした上で、ピントやポラック自身にも、彼らがつくり出す作品と同じようなものを感じると続けた。
「イスラエルには徴兵制があるけれども、抜け道もあるそうなんです。蝶ネクタイを着けてお坊ちゃんみたいな恰好をして精神的に不安定であるというキャラクターを自分で演出して演じて、徴兵検査で自分がいかに兵役に不適合であるかをアピールする。日本でもかつては兵役を免れるためにしょうゆを一升飲んだ、なんていう話を聞いたことがあります。しょうゆ一升飲むって想像もつかないけれど、でもなんだか想像できちゃうじゃないですか。体がこんな風になって動けなくなる。……インバルたちにも同じような空気を感じるんですよね。すごく退廃的な雰囲気の中で明るく振る舞う見世物小屋やサーカスのような舞台上に立っていることにこそ理由がある。そこにいないと生きていけない。あえてそこを選ばないと生きていけない環境に私たちは立たされているのだ、という。そういう風に見えるんですよね」。
しょうゆのくだりで「体がこんな風になって……」と言いながら、森山は全身を振るわせてみせた。その瞬間、彼がこれまで演じてきた作品の数々が頭を去来する。去勢手術に失敗した男が愛を求め生きる姿を見せていく「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」や、ある日突然虫になっていた男の顛末を描いたカフカの代表作「変身」といった舞台に、突然女性にモテ出した29歳童貞男の紆余曲折を赤裸々に綴る「モテキ」、そして今回上映された「苦役列車」―― ダンサーとして卓越した身体能力を持ちながら、完全なる美をあっさり放棄して人間の持つ生々しさ、不完全さをとことん追求することを恐れないその姿勢。「苦役列車」の主人公、貫多の破天荒な人生を「アナーキズムじゃなく、ただまっすぐ生きている」と表現し、ダメ男ぶりをとことんリアルに垂れ流すように見せつけるその様は、どこか彼の描写するピントやポラックらの生き様とつながっていく。
淡々と話しているのにその言葉は熱く、飄々(ひょうひょう)としているのにその体が雄弁に物語る。文化交流使としての道のりはまだ、半分にも満たない。1年という月日を過ごした森山未來が、どのようなクリエイターとして日本に戻ることになるのか、今はまだ分からないが、コレオグラファーや演出家たちと意見を戦わせ、ときに同意し、ときに拒否し、人間の持つ美しさや醜さをひっくるめた生々しさを投影して一つひとつの作品をつくり上げる過程の只中にいる森山未來が今、とても伸びやかに生きているように見えることは確かだ。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?