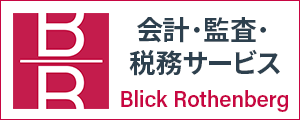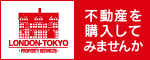第24回 妹を射殺した英兵? 許せます
第22回「男なら銃には銃、爆弾には爆弾だ」から、北アイルランド紛争の話を書いている。「まだ続けるのか?」と思われるかもしれないが、もう一度だけ書いておきたい。
カトリックとプロテスタント。住民の9割がどちらかの宗派に属する北アイルランドで、無宗教のマイケル・ホールさん(59)は少数派だ。彼は、どの宗派にも属さない利点を生かし、紛争が始まった1960年代末ごろから、「暴力では何も解決しない」と両勢力に働きかけを始めた経験を持つ。
「そしたら双方の組織に脅されてね。ひざをつぶすぞ、とか。後ろから撃れるんじゃないか、車に爆弾が仕掛けられていないか。毎日、それが気になってね」
そんな緊張の日々の中、彼は結婚する。相手の女性は、カトリック。同宗派の結婚ではないため、式場が見つからず、役所で挙式した。そのセレモニーで妻の両親は、とうとう姿を見せなかった。宗派を超えた結婚が激しい非難を浴びた時代。傷心の2人は、もっと広い世界を知ろうと、日本やアジアを2年半、旅して歩いた。
故郷に戻ると、両勢力を隔てる高い壁「平和の壁」は数が増え、分断はさらに強まっていた。学校も宗派別だ。ごく狭い地域ながら、「違う宗派の人とは話したことがない」という若者が急増していた。
社会福祉の仕事に携わりながら、ホールさんは「地域活動こそが対立終結への道だ。お互いがもっと相手のことを知らねば」との考えを強めたという。「とにかく双方が一緒に活動する場を」と、子供たちの演劇や旅行などの企画を手始めに、大勢の人を集めるようになる。
そのころ、ホールさんは、住民の声を拾った小冊子を作り始めた。その数は80種類以上になる。それを丹念に双方の住民に配り続けた。
あるとき、彼はこんなことを言われた。
「マイケル、この間の冊子、とても良かったよ。(小冊子で紹介されたIRAの主張の)一節はテレビで聞いたことがあった。そのスローガンだけを聞いたときは、すごく過激で、受け入れられないと感じたけど、冊子を読むと、彼らも地域のことを考えている。スローガンの前後には、ちゃんと文脈があるんだね」
やがて、双方から「敵側のことを書いた冊子がほしいんだ。彼らが何を訴えているのか、少し考えてみたいんだ」との声が頻繁に届くようになった。互いにスローガンを声高に叫びつつ、それ以上は相手のことを知らず、知ろうとしなかった時代。その中で、冊子は対立の土台を少しずつ崩し、相互理解を助けた。
「多くの人が紛争被害者としての経験を持ち、その相手と一緒にはやれないと言う。一方には、これ以上の悲惨な経験をしてほしくないと考え、話し合いに前向きな人もいる。どちらも理にかなっている。だから、問題は、その人に何が起きたかではなくて、どう対応するかの違いだと思う。そして、これが大事なんだけど、被害者だけが社会全体の将来を決めるのではないんだよね」
被害者感情が全面に出過ぎると、社会全体も感情的になり、やがて過激さを競うようになる。テロや暴力の容認は、過剰な被害者感情から生まれる。しかし、それではいけない……。それがホールさんの考えだ。そして、たぶん、それは北アイルランドに限ったことではない。実際、彼のもとには、イスラエルやパレスチナ、モルドバなどから視察団が次々と訪れ、地域和解の手法と経験を学んで帰った。
ベルファスト市の繁華街を少し離れた住宅街。家々の背後を縫うように、今も「平和の壁」と呼ばれる高い塀が走っている。地元の市民団体によれば、壁は現在35を数え、一つ一つは数キロの長さがある。
この壁が、名実ともに壊れる日はいつのことだろうか。
ベルファスト市内の墓地で、マーティン・リビングストンさん(51)に会った。元IRA活動家の墓石にペンキが投げつけられるという「事件」の直後のことだ。墓石の汚れを掃除しながら、元IRAの彼は言った。
「私はかつて2年半服役し、その間に14歳の妹が英軍に射殺されました。でも、今はもう、その兵士を許せます。真の和解は……たいへんですが、きっとできます」



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?