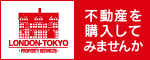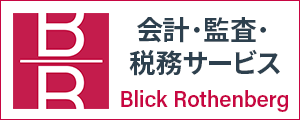第5回 クジラで母を泣かせた日。
英国で気分が悪くなるニュースの一つに、クジラ問題がある。「今も捕鯨を続け、クジラ肉を食べる日本人」を徹底批判する、あの「反捕鯨」ニュースのことだ。英国を中心とする反捕鯨キャンペーンは、感情的に過ぎ、気分が悪い。
最近では、日本の調査捕鯨船団が捕獲した2頭のミンククジラについて、豪州の首相が「母子クジラだ。気分が悪い」と批判する出来事があった。英国のニュースではないが、英メディアも大報道したから、ご記憶の方も多いと思う。
私自身は、欧米の反捕鯨論者には「欧米中心主義」の思い上がりを感じる。欧米も、過去には派手な捕鯨を行っていたし、「クジラを殺すな」と言うなら、「戦争で人を殺すな」と返したくなる。
でも、きょうは、そんなことを書きたいのではない。
子供のころ、郷里・高知の実家では、肉料理と言えばクジラだった。
昭和30年代後半から40年代初めにかけてのことだ。わが家も近所も、まだまだ貧しかったと思う。祖父母を含めて7人家族のわが家では、肉料理はめったに出ない。ごくまれに肉料理が並ぶと、それがクジラだった。たいていは、クジラ肉とジャガイモの煮付けである。
小学校の高学年になると、学校給食でクジラの竜田揚げが出た。「よくこんなに薄く切ることができたな」と思うほどスライスされたクジラ肉に、分厚い衣が絡んでいて、実にうまかった。
当時、豚肉や牛肉はまだまだ高根の花だった。「トンカツ」や「ステーキ」は、名前しか聞いたことがない。カレーに入っているのは鶏肉。ハンバーグと言えば、ボンレスハムのような形状の魚肉ソーセージを炒めたものだと思い続けていた。
◆ ◆ ◆
そんな時代のある日。
夕食の準備に忙しい母の脇で、私は鍋の蓋を開けた。湯気の中に、たくさんの野菜が見えた。
少なくとも肉料理ではない。祖父や祖母は病気がちで、自宅療養を続けていた。母は、そんな年寄りのために、いつも野菜中心の料理を作っていたのだと思う。もしかしたら、クジラ肉を頻繁に買う余裕がなかったのかもしれない。
とにかく、晩御飯のおかずが肉ではないと知った私は「ああ、また、げっしょりもん(がっかりするようなもの)かあ」と言ったのである。母は何も言わなかった。相変わらず忙しく動き回り、鍋の味を確かめ、「邪魔せんと、あっちへ行き」と私を追い立てた。
最後に帰郷したのは、5年ほど前だっただろうか。
わが家から路面電車で停留所をいくつか進むと、高知市民の台所「大橋通商店街」に着く。鮮魚店や八百屋が軒を並べるアーケード街を歩くと、クジラ肉を専門に売る店が健在だった。ショーケースに並んだ、クジラ特有の赤い色。店の灯りが、蛍光灯だったか、白熱灯だったかは思い出せないが、店構えも昔のままで、本当に懐かしかった。
そのとき、思い出したのである。
鍋の中を見て「げっしょりもんかあ」と言った数日後、私は母に連れられ、この通りを歩いた。
深緑色の電車を降り、アーケードをまっすぐ進んで最初の左角。夕方、おばちゃんたちでごった返す中、母はクジラ肉を買った。軒先から吊り下がった裸電球の下で、店員が経木(きょうぎ)に赤い肉を包んでいた仕草を、私は昨日のことのように思い出せる。
そして、私は分かったのだ。
私が鍋をのぞき込んだあの夕方、息子に「げっしょりもんかあ」と言われた母は、涙こそ流していなかったけれど、泣いたのである。自分が個人で背負ったものと、時代から背負わされたものと。その狭間で、十歳になるかならないかの息子の言葉によって、しばらく、立ちすくんでしまったのだ。
英国に来て、丸2年。
老いた母にあまり連絡もせず、私の親不孝は相変わらずだ。
母は、この「クジラ肉事件」を記憶しているだろうか。もし覚えていて、いま、「あんな言い方をして、ごめん」と謝れば、何か言葉が返ってくるだろうか。
これを書いているうちに、ロンドンは夜も更けてきた。日本は間もなく、夜が明ける。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?