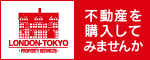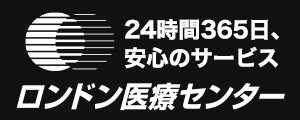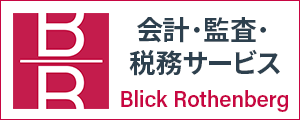年間総労働時間
日本人や英国人は、一体働き過ぎなのかそれとも働かなさ過ぎなのか。ワークライフ・バランスという言葉が流行っているが、どういったバランスが最適かは一概には言えない。仕事を通じて自己実現する人にとっては労働時間の多寡は気にならないということもあろう。また飲み屋でのコミュニケーションなども労働に入れると、労働時間の概念自体もしっかり定義しにくいものに思えてくる。
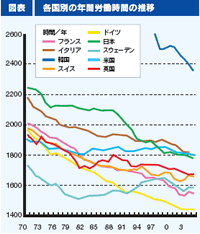 しかし確かなことは、日本人の労働時間が過去と比較して劇的に少なくなってきているということだ。右のグラフを見ると2005年の日本人の総労働時間は、1775時間(国民の祝日、週休2日、盆と正月に5日づつ休むと大体毎日8時間弱の労働になる)と韓国の75%で、米国、イタリアより少ない。さすがにバカンス3週間の独仏より多いが、英国より100時間ほど多いだけだ。この水準は、筆者が会社に入った86年より15%減少しており、父親世代が働き盛りだった1970年の大阪万博の頃よりも20%以上も減少している。韓国以上の労働時間といわれる中国人やインド人からみれば、それだけ働かなくて食うに困らない日本人や英国人は、資本や設備の力を借りて少なく働けるのでうらやましいとか、怠惰であるとか言われるであろう。韓国もこうした動きの後を追っているように見える。米国人よりも労働時間が短いことにも違和感があるが、これは長時間労働に従事する移民の有無が影響しているのではないかと考える。いずれにせよ、日本で労働時間の劇的な減少が起きているという事態は何を意味しているのか。
しかし確かなことは、日本人の労働時間が過去と比較して劇的に少なくなってきているということだ。右のグラフを見ると2005年の日本人の総労働時間は、1775時間(国民の祝日、週休2日、盆と正月に5日づつ休むと大体毎日8時間弱の労働になる)と韓国の75%で、米国、イタリアより少ない。さすがにバカンス3週間の独仏より多いが、英国より100時間ほど多いだけだ。この水準は、筆者が会社に入った86年より15%減少しており、父親世代が働き盛りだった1970年の大阪万博の頃よりも20%以上も減少している。韓国以上の労働時間といわれる中国人やインド人からみれば、それだけ働かなくて食うに困らない日本人や英国人は、資本や設備の力を借りて少なく働けるのでうらやましいとか、怠惰であるとか言われるであろう。韓国もこうした動きの後を追っているように見える。米国人よりも労働時間が短いことにも違和感があるが、これは長時間労働に従事する移民の有無が影響しているのではないかと考える。いずれにせよ、日本で労働時間の劇的な減少が起きているという事態は何を意味しているのか。
労働時間が減ったとしても
労働時間を減らしても、機械など資本投下した道具を使って付加価値の高い製品を作ることで収入を増やせるのであれば生活のレベルは維持か、もしくは向上する。ドイツがそうである。日本でも、70年代や80年代と比べても生活水準は全体としてみれば向上していると思う。ただ90年代以降の不況期における労働時間減少は半分程度が正社員のパート化によるものだ(今や日本の雇用の3分の1はパート、フリーターである)。企業の残業減らしや若年労働者の雇用減少も影響していると思われる。生活レベルを維持できないワーキング・プアが問題となる所以である。
ちなみに英米では労働時間は80年頃から減少し、その後は横ばい圏内にある。日本の生活レベルは英米と比べて遜色はないように思えるが、だとすれば全く問題はないと言えるのだろうか。
中年を覆う疲労感
労働時間が減り生活が豊かになったはずの日本人には何か疲労感がある。筆者が中年でそう感じるだけなのかもしれないが、同僚と話してもそう言う。労働=苦痛、余暇=快楽として、労働を対価として得た賃金で余暇を楽しみ、それを最大にするのが人間の幸福という功利的な人間観は、デスクワークに従事する中間層の増大、さらにホワイトカラーの増大により意味を半分失いつつあるからだ。半分というのは、一般の社員は定時が来れば帰りたいし、残業もしたくはない。英人の秘書は夕方5時を過ぎて残ることはまずない。勤務時間が午後5時まででも4時50分から帰り仕度を始めるのが常である。
一方で仕事が趣味のような会社幹部は多い。定時退社しても年俸制で、飲み屋でも、休日でも仕事のアイデアや構想を練っている。ただ、そうした構想が必ずしも実現できず、会社組織の維持に汲々とするための小アイデアしか求められていないことが多いのが問題である。
高度成長期のようにリスクをとるダイナミズムが多くの企業で欠落している。これが疲労感の原因だと思う。サービス残業は論外としても、成長の行き詰まりに対する回答を考えるような仕事がなければ、余暇は単なる享楽にしかならないのではないか。結局、形だけの労働時間短縮を景気変動や欧米の真似を理由にして行うのでは、大企業病を更に悪化させることになる。経済政策では表面の統計のみならず、統計の裏にある実際との乖離も考えて施行するべし、というのが英国財界のお役所批判だが、最近の経団連など日本財界の規制緩和要求はそこまで踏み込んでいるようには見えないがどうだろうか。
(07年6月30日脱稿)
| < 前 | 次 > |
|---|

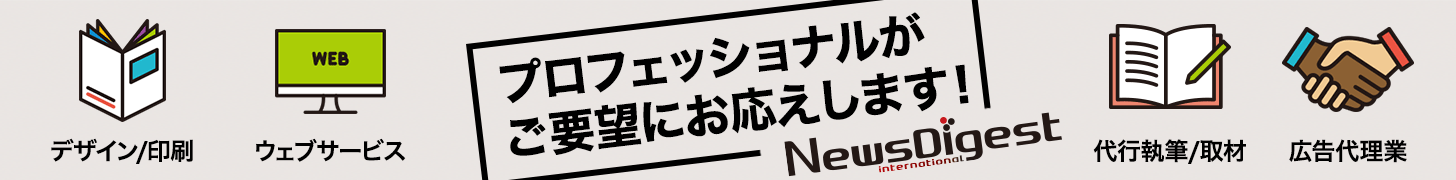

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?