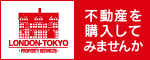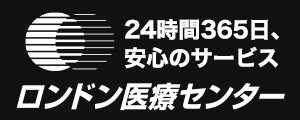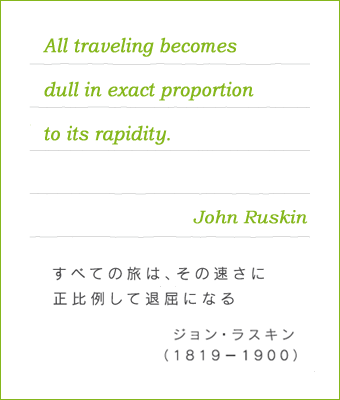
随分前のことになるが、世界の文学の故郷を訪ねる日本の新聞の連載ルポで、起伏に乏しい英国の田園風景のなかを長時間ドライブし続けて退屈であったとする文章を読んだ覚えがある。この記者が目的地まで専用飛行機にでも乗って飛んだなら、そして、移動時間の短縮によって生まれたフリータイムをショッピングや観劇にでも費やすことができたなら、そんな感想は漏らさなかったろう。これと同じ感覚で、我々も長距離バスや鈍行列車の旅は、退屈=「dull」だと思い込みがちである。
だが、注目。ラスキンは、まさにその反対を言った。駆け足の旅こそ「dull」だと主張する。普通の感覚ではない。ターナーやラファエル前派の美術を支持した批評家は、世の常識に惑わされぬ鋭い目と、独自の感性の持ち主であった。
旅とは、小さな発見の連続である。風景や自然にも、風俗や人情にも。車窓に躍り、戯れる光の微妙な変化にさえ、発見のときめきがあるものだ。発見は感動を伴う。旅とは、感動する心の軌跡である。感動の機会を奪われれば、旅はただの移動になってしまう。そして、移動が旅の意味を失って、ただの移動に堕した時、それは「退屈」以外の何物でもなくなるのだ。
私は、まあこれは貧乏が必然的になせる業でもあるのだが、パリにもアムステルダムにも、バスで出かけたことがある。すると、道中に見えてくるものが実に多いことに気づかされた。夜のドーヴァー海峡を越える時には、各国(とりわけ東欧)のプレートをつけた大型トラックの多さに、欧州経済の最前線を見る気がした。飛行機でもユーロスターでも何度も往復したロンドン~パリだが、道中に得る発見や感動に関しては、こちらの旅の方が遥かに収穫が大きかった。
「タイムイズマネー」を説いたのは、米国のベンジャミン・フランクリンだったが、時間を経済性のみで計るこの手の考えが、20世紀を頂点とする米国の繁栄を築き、今もなお、世界はその延長上に成長を目する。
だが、まさしくその20世紀の到来を拒否するかのように世を去った(1900年に逝去!)ラスキンという英国の巨星に、私はこの国が長く大切にしてきたものを教えられる気がする。ガーデニングや茶を啜るひと時にも通じる、大袈裟でない静かな感動、人としての穏やかなる心の昂ぶりである。
長旅を「退屈」としか感じられない感性が世を牛耳ると、それこそ世界は感動を忘れた「退屈」の墓場と化す。ラスキンが美術批評から後に社会思想家として社会改良の理想を説き、実践するようになるのは、当然の道だったのかもしれない。
| < 前 | 次 > |
|---|

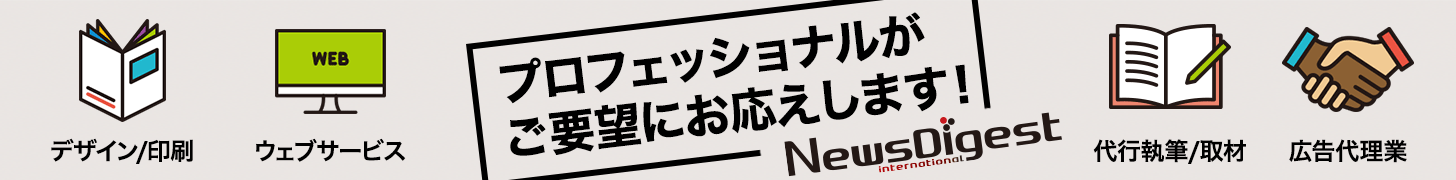

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?