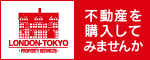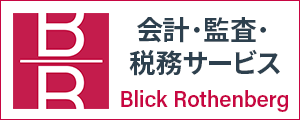演劇輸入大国、日本。近年、日本の作品、演出家が海を越え、ここ英国に渡ってくる数は少しづつ増えているとはいえ、その絶対数はいまだ少ない。そんな現状に風穴を開けるべく、一つの新たな形が提示された。「ウーマン・イン・ブラック」ロンドン公演。今年9月、英国作品の日本版を、そのままの形で本場英国に持ってくるという、挑戦的な企画が実現する。英国人演出家による、英国の物語の日本版上演。ここで問われるのは、何より日本演劇人の「演技」ではなかろうか。その「演技」勝負の芝居に真っ向からチャレンジする俳優の一人、上川隆也が1月末、本公演の記者会見のためロンドンを訪れた。「何を演じていても面白い」と言う根っからの役者上川に、本作品にかける意気込みを聞いた。
(取材・文: 村上祥子)
1965年5月7日、東京都生まれ。中央大学在学時にアルバイトで学校廻りの劇団に所属し、日本各地を巡業する。その後1989年、演劇集団キャラメルボックスに入団。1995年にはNHKドラマ「大地の子」主演で注目を集め、以降は映画・テレビの分野にも活躍の場を広げる。一昨年2006年にはNHKの大河ドラマ「功名が辻」で主演の山内一豊役を演じるなど、舞台、テレビ、映画の各分野で活躍する実力派俳優である。
ウーマン・イン・ブラック ―黒い服の女―
 とある劇場の舞台上。老弁護士キップスが、若い俳優相手につたない口調で自らの経験を語っている。キップスは若い頃、誰にも語ることのできない恐怖の体験をし、それ故に悪夢に悩まされる日々を送っていた。彼は家族らにすべてを語ることで、そんな記憶から解放されようと決意する。その練習を行うため、若い俳優を雇ったのだが、話のあまりの長さとキップスの語りのつたなさに、俳優はある提案をする。俳優が若き日のキップス(ヤング・キップス)を演じ、その時にキップスが出会った人々をキップスが演じるという舞台の形で、この話を語ろうというのだ。かくしてキップスの恐怖の体験が上演されることになった……。
とある劇場の舞台上。老弁護士キップスが、若い俳優相手につたない口調で自らの経験を語っている。キップスは若い頃、誰にも語ることのできない恐怖の体験をし、それ故に悪夢に悩まされる日々を送っていた。彼は家族らにすべてを語ることで、そんな記憶から解放されようと決意する。その練習を行うため、若い俳優を雇ったのだが、話のあまりの長さとキップスの語りのつたなさに、俳優はある提案をする。俳優が若き日のキップス(ヤング・キップス)を演じ、その時にキップスが出会った人々をキップスが演じるという舞台の形で、この話を語ろうというのだ。かくしてキップスの恐怖の体験が上演されることになった……。
1月25日金曜日、ロンドン中心部にある由緒ある劇場、フォーチュン・シアター。つい先程まで記者会見が行われていた、まさにその舞台上で今回のインタビューは行われた。まっすぐにこちらを見つめる強い視線、眉間にしわを寄せながら答えを探す姿勢、長い間を取ってからゆっくり話し始める独自のテンポ、そして選ぶ言葉のユニークさ。そのどれもが穏やかで誠実な人柄とともに、強烈ではないが独特な「色」と、その奥底に潜む役者としての情熱を物語っていた。
「セットの風景に、既視感を覚えた」
ロンドンに着いたのは前日の木曜日。そのまま夜は本場英国の「ウーマン・イン・ブラック」を鑑賞し、土曜日には日本へ戻る。そんな超の付くハード・スケジュールのなか、上川は「時差ボケは全くありません。日本でもめちゃくちゃな生活ですから」とからっと笑った。
「ウーマン・イン・ブラック」は、今年で19年目のロングランを迎える、英国発ゴシック・ホラーの2人芝居。日本では1992年に初演。大評判を呼び、以降数年ごとに上演回数を重ねている人気作品だ。1999年、2003年と同作品を演じてきた上川にとっては、ロンドン公演を含めた2008年公演が3回目の参加となる。
今回のロンドン公演の話を最初に聞かされたのは、2003年大阪公演の千秋楽の直後だった。演出家、ロビン・ハーフォード氏の送別会をやっている最中に耳にしたが、その時は「単なるリップサービスだと思っていた」という。そして正式に出演依頼がきたのは昨年の秋。その時の心境を尋ねると、長い、長い沈黙の後にこう言葉を紡いだ。
「喜びが無かった訳では、もちろん無いです。凄いと思いましたけれど、正直どこか他人事でしたね。別にナショナリズムがそれほど強い方ではないと自認しているんですが、それでも日本人がフォーチュン・シアターに乗るっていうことには快哉を叫びました。けれどそれが自分だと思うと、振り上げた腕をおずおずと戻さざるを得ないというか(笑)」。
それは恐怖心からくるものなのだろうか。「恐怖心、……というのではなくて……。自分でいいのかなって思うんですよ。それはどんな作品でも。この作品に携わるのが自分でいいのかなって思ったところからが常に出発点なので、今回もロンドンに行くのが俺でいいのかな、という気持ちです。もう来ちゃいましたので、後にも先にも逃げようがないんですけれども」。
自分でいいのか、そんな気持ちを燻(くすぶ)らせていた上川だったが、その思いはフォーチュン・シアターの舞台 に立った瞬間に消え失せた。「この場に立ってみたら、あれって思ったんですよね、現金なもので。この風景に、既視感があるんですよ。ここに立っていた覚えがあるんです。このセットの中に……。で、にわかに『ここでならできる』って思えちゃったんです」。ステージに乗った瞬間、ロンドン公演の話を聞いた時に感じた「意義や意味や重さ」が喜びに転換された。「ここでやったことがあるのかも、という幸せな誤解すら感じた」。今ではこの舞台に立つことが「ちょっと楽しみ」になってきたという。
「シンプルさ故の豊かさ」
英国初演から19年。時代は変わり、テレビや映画のみならず、舞台でさえも最新SFX技術を使った「恐怖」を味わえるようになった。にもかかわらず、簡素な舞台装置、役者は2人きりというシンプルな構成の芝居がいまだに支持される理由は何なのだろうか。演じる側として感じる、この作品の持つ独特の魅力とは。
「シンプルな『ウーマン・イン・ブラック』という入れ物に自分を入れてみると、その度に自分が今、どんな状態でいるのかをあぶり出されるような感じがあるんです」、そう上川は分析する。だから演じるごとに、この物語に対する感じ方は大きく変わるのだという。具体的にはどう変わるのか、と聞くと、「ええ、そうですよね。それを具体的に聞きたいんですよね」と言いながらにやりと笑って次の例え話を聞かせてくれた。
「例えば、初めて行く場所に、自分の家から地図を頼りに出かけて行ったとして、最初はたどり着くことしか考えていないと思うんです。それが2度3度と通って地図を手放せるようになると、今度はその目的地に行く道すがらに目を向けられるようになるんですよ。そうやって出発点と目的地の間の風景を知っていくことができる。さらに、しばらく振りにその道を歩いた時に感じる、風景の受け取り方の差っていうのも、きっとあると思うんです。たどる道は同じで目的地も同じはずなんですけれども、1999年にやった時と2003年にやった時の感慨が違ったのと同じように、今回の2008年にも、きっとそれがより違った形で起こるだろうなという思いがあるんです。でもきっとそれが感じられるのは、自分が変わったからだということの証に他ならないと思うんですね。そういったことをとても強く感じさせてくれる作品なんです」。
今でも新鮮味はあると思うか、そう重ねて問うと、常にゆっくり考えてから言葉を発する彼には珍しく、「新鮮味というよりも普遍性」という答えがすぐに返ってきた。この芝居の魅力、それは何より「シンプルさ故の豊かさ」、そして「イマジネーション」だと上川は言う。そして舞台上に置かれた、芝居の中でさまざまなものに見立てられる大きな籠をポンポンっと叩きながらこう続けた。
 「この籠だからこそ想像できる馬車や列車がある。400以上の机や汽車や馬車が、お客様それぞれには見えていると思うんです。それはどんなに精緻につくられたハリウッドのCGにも負けていないと思うんですね。そのお客様が頭に描かれたものは、たぶん現実の何よりも豊かなんです。その豊かさ故に、自分自身の今の状況すら浮き彫りしてくれるキャパシティをも持ち得るんでしょうし、そこがお芝居の原点に肉薄しているような感もあって、やる度に楽しいのもそのためなんでしょう」。
「この籠だからこそ想像できる馬車や列車がある。400以上の机や汽車や馬車が、お客様それぞれには見えていると思うんです。それはどんなに精緻につくられたハリウッドのCGにも負けていないと思うんですね。そのお客様が頭に描かれたものは、たぶん現実の何よりも豊かなんです。その豊かさ故に、自分自身の今の状況すら浮き彫りしてくれるキャパシティをも持ち得るんでしょうし、そこがお芝居の原点に肉薄しているような感もあって、やる度に楽しいのもそのためなんでしょう」。
共演者との化学反応
今回、上川と共演するのは斎藤晴彦氏。1992年の日本初演以来、すべての公演に出演している日本版「ウーマン・イン・ブラック」の生き字引的存在だ。複数の役者が組み合わさった時に生まれる化学反応次第で、舞台は如何ようにも変わるとはよく言われること。特に出演者は2人だけというこの芝居では、その違いが顕著に現れるのではなかろうか。
「化学変化の中には、きっと『混ぜるな危険』と表示しなきゃいけない化学変化もあると思うんです。……でも斎藤さんとのそれは、どんなに大量投与したところで、安心感しかもたらされないっていう化学変化なんです。ものすごくいい香りが漂ってくるとか、ものすごく栄養素が豊富とか。今回はそれがますます深まりそうな予感がしています。すごくいい香りで体にもいい、おまけに環境にも優しい、みたいな(笑)」。
 共演者の斎藤晴彦氏とともに
共演者の斎藤晴彦氏とともに上川にとって1999年の初演は、自身の劇団を飛び出し、外部の舞台に初めて出演した記念すべき作品だった。片や相手役の斎藤氏は超ベテラン。老弁護士と若手俳優という舞台上の設定とも相まって、上川の純粋でけれん味のない演技が評判となった。それから9年。上川も各メディアで活躍する実力派俳優の一人と呼ばれるようになった今、2人の関係性も必然的に変わってくるのではないだろうか。この質問に、上川は少し俯いて逡巡した後、ゆっくりと、しかしきっぱりこう言った。「年齢って、何の支えにもならないんです」。
「役者なんて、何をしてきたかでしか問われない生業ですから、40過ぎたからって良い芝居ができるわけでもないですし。(関係性の変化を)感じられるとしたら、それはきっと斎藤さんと僕の2人共が、良い時間を過ごした結果なんだろうと思うんです。だから今回、良い空気を斎藤さんとの間につくれたのだとしたら、僕はこれまでの5年間を、肯定できると思うんです。今の自分が何をできるのか、それを早く見てみたいですね」。
日本ならではの「湿度」
海外でつくられた芝居が日本で上演される場合、日本の文化背景や日本人の感覚に合わせ、演出や脚本を変更することがある。しかしこの「ウーマン・イン・ブラック」は、オリジナル作品の演出家、ロビン・ハーフォード氏が日本における全公演の演出を直接手掛けていることもあり、日英における差異がほぼないことで知られている。しかしだからといって日本人が、英国人がつくった、英国を舞台にした物語を、英国の劇場で演じることに何の障害もないかと言えば、それはまた別の問題だろう。本場に日本版を持ってくることに関して、上川はスポーツに例えて、こう表現した。「スポーツだと、場所が変わっても道具は変わらないですよね。でもこの場合は道具が違うんです」。前夜に英国版を観劇した際にも、やはり大きな違いを感じた。端的に言うならば「ドライだな」と思ったのだそうだ。日本の作品には、もっと「湿度」があるという。
「見終わってすぐ感じたのが『ドライだな』ということでした。これはオーディエンスの反応もしかりなんですけれども。幕が下りた瞬間にワーっとオベーションと拍手があるんですが、でもみんな「面白かったね~」バーっと出て行くんですよ。でも日本の観客の皆さんは、もう少しこの物語や、ドラブロウ家の悲劇や、子を亡くした母親の気持ちにまで思いを馳せて劇場を後にしているような感覚があるんですね。そういった、登場人物に対するとらえ方が全く違うんだなというのも湿度として感じた部分だったんです」。
そしてもう一つ、演じ方にも「ドライさ」を感じた。その昔、恐ろしい体験をした老弁護士キップスの若かりし頃を、若い俳優が劇中劇として演じるこの芝居、上川はその若い俳優の演技に違いを感じた。
「最後、うちひしがれた若かしり頃のキップス(ヤング・キップス)が毛布にくるまれて自分の経験を語る時に、自分が怖かったことを語っているように見えたんです。なんで自分がそんなことを経験しなければならなかったのかって考えているように思えた。その前の打ち明け話に大きく心を動かされているわけではないんじゃないかって感じてしまったんですよ。……だからといって国民性みたいなものに押し込めたくはなくて……。もしかしたら僕と斎藤さんがやっているお芝居が、より湿度の高いものになってしまっているのかもしれない。でも僕自身の気持ちで言うならば、僕はここまでドライにこの物語とは向き合えないっていう気持ちがあるのは確かです」。
だからと言って、どちらの方が良い、という訳ではな い。どちらが正解か、そんなことを考えるのは「むしろ愚か」で「寂しい行為」だと上川は言う。演じる人間の数だけ違う作品が存在する。そこにこそ、この「ウーマン・イン・ブラック」の魅力、19年続いた今でも人々を惹き付けて止まない人気の秘密があるのかもしれない。
「何をやっても面白い」
 役者として20年のキャリアを誇る上川。その間、演じた役は実に幅広い。時代劇では華麗な殺陣を披露、シリアスな社会ドラマでは世の中の矛盾と戦う役を真摯に演じ、コメディ・ドラマではゲイの役も飄々とこなす。あらゆる役柄を自然に演じきる上川の演技力に、役者としての力量を見ると同時に、彼の作品選びの基準とは何なのか、役者上川隆也としてのこだわりとは何なのかを問いたくなってくる。
役者として20年のキャリアを誇る上川。その間、演じた役は実に幅広い。時代劇では華麗な殺陣を披露、シリアスな社会ドラマでは世の中の矛盾と戦う役を真摯に演じ、コメディ・ドラマではゲイの役も飄々とこなす。あらゆる役柄を自然に演じきる上川の演技力に、役者としての力量を見ると同時に、彼の作品選びの基準とは何なのか、役者上川隆也としてのこだわりとは何なのかを問いたくなってくる。
「役者で食える人なんていうのは、本当に一握りだと思うんです。それだけでも幸せだと思うんですけど、さらに舞台にもテレビにも映画にも声をかけていただいて……。もったいないじゃないですか、やらないのは」。
こだわりを尋ねた答えがこれである。2006年にはNHK大河ドラマの主役まで務めた役者にしては、あまりに謙虚な言葉だ。こういう役をやりたい、という働き掛けはしないのか、と重ねて問えば、やはりというべきか、「僕は全くもってアクティブじゃないです……」という、あくまで受け身な言葉が戻ってきた。しかし、続く言葉には謙虚さとともに、上川の、演じることに対する自負にも似た強い気持ちが垣間見える。
「よくいらっしゃいますよね、自分でプロデュースまでして、すべて作品をつくりあげていかれる方とか。そういうアプローチが一切できない性質(たち)の人間であるということを自認しておりますので(笑)。お声掛けいただくのを常にお待ち申し上げている次第なんですが。でもだからこそ、掛けていただいた声にはなるべく答えたいと思うんです」。
来るものは拒まず。でも来たものには全力で取り組む。上川にとっては、「何を演じるか」ではなく、「演じるということ」そのものにこだわることこそが、何より大切な役者としての在り方なのではなかろうか。今回、本場で演じることの難しさを尋ねた時の上川の言葉に、「演じること」に重きを置く、もっと言うならば演じられればそれでいいのだという彼のシンプルかつ明確な役者哲学を見た。
「もちろん細かいことを言えば、こんなアジアの人間が、キップスさんだジェロームさんだと呼び合うこと事体が珍妙だと思うんですよ。……でもそれは結局細かいことでしかないのかなという気もしているんです。むしろ、日本のカンパニーをここに乗せてみようと思ったロビンさん始め、イギリスのスタッフの方々の思いの方をありがたいと思いますし、その思いに応えてここで芝居をすることの喜びの方が何よりも上回っています」。
最後に、月並みながらどうしても聞きたかった、こんな質問をした。役者上川にとって、「演じること」とは?
「……一番楽しいことですかね。何年経っても、一番面白いものの座がお芝居ってものから動かないんです。始めてから20年ですけれども、オフの時間の方が楽しくなってしまったなっていう局面が一度も訪れていないんです。どこでやっても、何をやっても面白い。面白いとしか言いようがないですね」。
あくまで受け身、でも演じることにはどこまでも貪欲な役者、上川隆也。きっとこれからもありとあらゆる役柄を真摯に、謙虚に、思う存分楽しみながら演じていくのだろう。
インタビュー中、上川は自らを「演者」と呼んだ。「俳優」でも「役者」でもなく「演ずる者」、「演者」と言った、その真意は分からない。だが、ただ演じることを純粋に楽しむ彼には、似つかわしい言葉のように思える。9月、フィールドも「道具」も違うここ英国の劇場で、それでも思い切り演じることを楽しむ上川の姿が、見えた気がした。
演出家、ロビン・ハーフォード氏に聞く
 もともとは、クリスマスにゴースト・ストーリーを上演しようと考えたのがきっかけでした。新作でも小説の戯曲化でも良かったのですが、予算が1000ポンドしかなかったんです(笑)。スティーブン(・マラトレット。脚色担当)が持ってきたこの小説は素晴らしかったけれど、何と言ってもこの低予算で抑えるには登場人物が多すぎた(笑)。そこでスーザン(・ヒル。原作者)に戯曲化の了承を得た後、登場人物を2人にまで削ることにしたんです。
もともとは、クリスマスにゴースト・ストーリーを上演しようと考えたのがきっかけでした。新作でも小説の戯曲化でも良かったのですが、予算が1000ポンドしかなかったんです(笑)。スティーブン(・マラトレット。脚色担当)が持ってきたこの小説は素晴らしかったけれど、何と言ってもこの低予算で抑えるには登場人物が多すぎた(笑)。そこでスーザン(・ヒル。原作者)に戯曲化の了承を得た後、登場人物を2人にまで削ることにしたんです。
日本と英国は、片や歌舞伎の国、片やシェークスピアの国ですから、さまざまな面で違いはあります。そこが面白い。本作品は19年間、上演され続けているわけですが、「イマジネーション」を常に新鮮な状態に保つため、キャストは9カ月ごとに変えることにしています。その点では、日本版の制作はまさに「究極のキャスト・チェンジ」と言えますよね。
私は本作品の演出をするために何度か日本を訪れていますが、日本で思ったのは、若い女性が観客のほとんどを占めているということ。個人的には、色々な年齢層の方々に観てほしいと考えています。こちらでは学生席を非常に安価で提供しているので、子供たちがたくさん観にくるんです。難しい言葉を使っている部分があるので、すべては理解しきれないんですが、それでも夢中になって観ている。だから私は劇場側に「いくら高い席があってもいい、安い席さえあれば」っていつも言っているんですよ。
(上川)隆也さんは非常に謙虚で、良い役者だと思います。共演の斎藤さんのことを真摯に信じているのがこちらにも伝わってくる。そうそう、日本で稽古していた時、隆也さんがちょっと用事が……とだけ言って静かに出て行ったことがあったんです。その後テレビを観ていたら、何と華々しい授賞式に彼が出てるじゃないですか。何も言わずに出て行くところが、いかにも彼らしい、と思いましたね。年齢が40歳を過ぎていたって何の関係もない。隆也さんは今でも変わらず若々しいし、ヤング・キップスに見えさえすれば、年齢なんて何歳だってかまわないんです。
ロンドン公演決定記者会見

これまですべての日本公演で制作を担当、ロンドン公演にも企画制作として携わる(株)パルコからは、祖父江友秀氏(写真右)が参加。「怪談好きで、『語り』が成立している英国と日本は近しいから」と、日本における本作品の人気の理由を語った

「二度と巡ってこないチャンス。このチャンスを楽しみたい」と身振りを交じえ、真剣に語る上川

本公演は、在英国日本国大使館の後援が決定したことに加え、日英交流150周年記念事業「JAPAN-UK 150」の主要イベントの一つとしても実施される予定
The Woman in Black
原作: スーザン・ヒル
脚色: スティーブン・マラトレット
演出: ロビン・ハーフォード
出演: 上川隆也、斎藤晴彦
後援: 在英国日本国大使館
企画制作: 株式会社パルコ
制作協力: 株式会社ミーアンドハーコーポレーション
公演日程: 2008年9月9日(火)~13日(土)
場所: ロンドン、フォーチュン・シアター
The Fortune Theatre, Russell Street, London WC2B 5HH
最寄駅: Covent Garden
http://www.fortune-theatre.co.uk/
チケット販売: 3月31日より劇場及びインターネット上でチケット販売開始。
電話予約 0870 060 6626(英語のみ)。
上演3週間前からは、The Ambassador Theatre Groupで 日本語専用ホットラインを設置予定。
* ロンドン公演では、英語字幕あり(Dress Circleのみ)


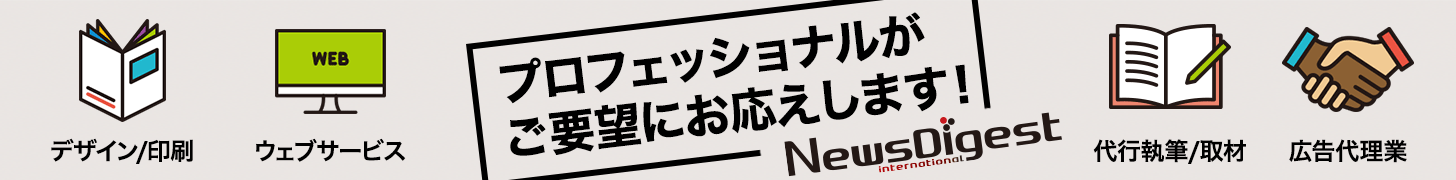

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?