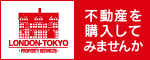第45回 残り少ないロンドンの日々。
少し前の金曜日のことだ。
夜11時ごろ、地下鉄オックスフォード・サーカス駅のホームで電車を待っていると、ちらちらとこちらを見る人がいる。妙齢の女性が3、4人。「誰だっけ?」と思って見返すと、向こうは目をそらす。
やがて電車が来て、30分ほど揺られた。そして、下車駅で改札を抜けたときである。右斜め後ろから、日本語が話しかけてきた。
「あの、高田さんですよね?」
さっきの女性たちの1人だ。連れの女性はやや離れて立っている。そこだけが明るい駅の出入り口。人込みの中で、彼女の声は続いた。
「実は乗る前から見てたんです。あ、高田さんだって、驚いちゃって。これはきっと運命だ、今を逃すともう会えないかもしれない、ここで声をかけなきゃ、って」
驚いたのは、私である。この年になって、妙齢の女性に街頭で声を掛けられるとは。しかも、相手は「ウンメイ」などと言っている。
私が英国に来たのは、2006年2月下旬である。渡英して3年が過ぎた計算だ。一方、本誌で連載を始めてからも、ちょうど1年が経過した。両方とも、なかなか切りがいい。
そんなことを考えているうち、本社から声が掛かった。「日本へ戻ってこい」という人事異動のお達しである。そして3月1日付で、東京に戻ることが決まった。
月並みな言葉だが、3年なんて本当にあっという間である。「あれもやりたい、これもやりたい」と考えていたのに、ほとんど何もできぬうちに月日だけが瞬く間に流れ去った。
一方、小欄の読者からは、この1年、たくさんの激励や感想を頂いた。パーティーなどで直接励ましの声をもらったこともあるし、編集部を通じてメールで声を届けてくれた方もある。言うまでもないことだが、どの内容も温かく、うれしかった。
とりわけ、声が多かったのは、第37回「運命が引き起こす奇跡」である。箱根駅伝への出場経験を持つ、ロンドン在住の作家、黒木亮さんの学生時代を綴った回だ。たとえば、私と同い年の男性からのものには、こう書かれていた。
「……まさに自分の思いを全部代弁してくれているかのようなコラムでした。養父から出生の秘密を打ち明けられるシーン。ロンドンに実母から手紙(写真)が届くシーン。そして、初めて実父に出会うシーン。字数は少ないですが、行間が非常に深く、何度も読み返しては、涙が頬を伝わりました」
また、60歳の女性はこんなメールをくれた。
「……両方の親御さんに感情移入をしてしまいました。シュークリームの箱を壁に叩きつけられた時、どんな思いをされたのだろうか、また初めて手紙を受け取られたお母さんはどんなにうれしかっただろうか、とか……。どちらもいい方たちですね。それもこれも金山さん(黒木さんの本名)が真っ当に成人されたからにほかならないと思います。こうして入力していても思わず涙がこぼれてきます」
もちろん、これらの感想は「黒木さんの人生に感動したからこそ」ではあるが、文章の書き手にとっても、これ以上の褒め言葉はない。
「ウンメイ」の女性たちは、実は小欄の大ファンだった。そのうちの1人が、私を某所で見掛けたことがあったらしい。彼女たちとは後日、ロンドン市内のレストランで小宴を持った。中には、私と同じく、間もなく日本へ戻る人もいた。
たわいもない談笑の最中、ビールで顔を赤くした1人が突然、「高田さん、あなたの夢はなんですか」と質問をぶつけてきた。
私には今もちゃんと夢がある。夢想というよりは現実に近く、実現性という意味では儚く、そして両手からこぼれ落ちていきそうな感じではあるが。しかし、夢は語ってこそ形になるものだし、運命は自分で切り拓いてゆくものだ。
後日、彼女たちから届いたメールにも、それぞれに夢のことが書いてあった。それを読みながら、私は少し、こみ上げるものがあった。マラソン・ランナーだった黒木さんがそうだったように、運命を切り開く歩みの中にこそ、私たちは生きる価値を見つけ、共鳴するのだと思う。
そんなことを考えながら、残り少ないロンドンの日々を過ごしている。

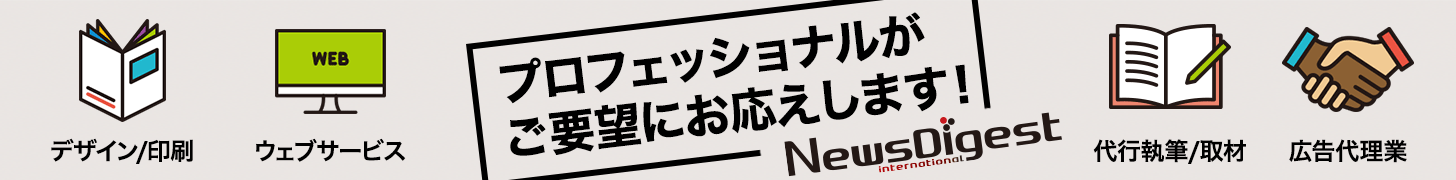

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?