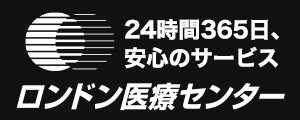第34回 おたる政寿司のカウンター。
過日、ロンドンで「Sushi Awards 2008」という催しがあり、足を運んでみた。世界各国の寿司職人7人が自慢の腕を競う試みだ。
「日本代表」は、北海道小樽市の「おたる政寿司」3代目、中村考志さん(29)だった。この店の名前は懐かしい。中村さんが着ていた白衣の左胸に店のロゴを見つけたときは、本当にうれしかった。
小樽で暮らしたのは、北海道新聞社に入ったばかりの1986年4月からの3年半である。今では全国屈指の観光地になった小樽も、当時は寂れた地方の都市に過ぎなかった。赴任初日、街は深い霧に包まれ、それが寂寥感を倍増させていた。
職場に初めて足を踏み入れ、挨拶すると、壁側にいたデスクが「おめえ、挨拶くらいはできるみたいだな」と言う。いきなり「おめえ」である。
「でな、最初の3カ月、君の担当は水族館だ」
事件事故の修羅場や深層・潜行取材が明日にも始まると思っていた私は、拍子抜けした。当時も今も「おたる水族館」は全国でも指折りの規模と展示を誇る。「でもなあ、取材の相手はトドやペンギンかぁ」。それでも、私も意地みたいなものがあって、来る日も来る日も水族館の記事を書いた。「ペンギンの赤ちゃんが生まれた」「イルカが芸を特訓中」とか、そんな感じである。何しろ、全国有数の施設だ。1種類ずつ取り上げても、数カ月は持ちそうである。
原稿は次々にボツになった。ペンでマス目を埋めた原稿用紙を持っていくと、おめえのデスクは、サーっと見て、大きなごみ箱に丸めて捨てる。「どこが悪いんですか?」と聞くと、「自分で考えれ!」と一喝。とにかく怖い。何回もそれを繰り返し、「やっと分かってきたな」と言ってもらうと、心底ほっとした。
こんなこともあった。
おめえのデスクから早朝に電話である。そして「タイムス見たか?」と言う。今は廃刊となったが、当時は「北海タイムス」がライバル紙で、その朝刊を見たか、と言うのだ。いやな予感がした。「見てません」と言うと、「見てから電話すれ!」と電話が切られた。警察署の横に住んでいた私は「タイムス見せて」と署に駆け込んだ。1面、社会面、小樽版……。重要な記事は見当たらない。私は再び受話器を握った。
「見ました」と私。
「やられてるべ」と、おめえ。
「いえ、何も出てませんが」「タイムスに先を越されてっだろ」「何も出てません」「小樽版を見ろ。出てるべや」「??」「小樽の都通り商店街に雛祭り人形が並び始めた、って。出てるな?」「はぁ」
すると、ここから大声に……。
「おめえ、少し前に言っただろうが。雛人形が店先に出てるから小樽版で記事にしろ、って。季節ものの記事だからって、適当にやるんじゃねえ。こういうものであっても先にやられたら悔しいと思わないのか?どうなんだ?悔しいと思わなかったら記者じゃねえぞ」
おめえのデスクには多くのことを教わった。狭い社内での出世には縁がない方だったが、とにかく厳しく、がんがん怒る。それでいて、理不尽な叱責はない。そして「街を歩け。外に出ろ。記者クラブに籠もるな」と再三、言われた。
「1日に3人は新しい人に会え。同僚と飲んで楽しいか?どうせ飲むなら街の人、ふつうの人と飲め。記者が群れるのは見苦しい」
そんな最中のこと。夜、ほかにだれもいない職場で、私はさんざん、おめえのデスクに絞られた。そして、消沈する私を置いてデスクは外に行き、寿司折りを手に帰ってきた。
「まあ、食え」
寿司折りは「政寿司」である。そのころから知られた高級店だ。自分はさっさと席に戻り、私には知らん顔で仕事を続けていた。
その後、一度だけ、このデスクと政寿司に行き、カウンターに座ったことがある。転職組とはいえ、ろくな社会経験のなかった私の目に、重厚な白木のカウンターはまぶしかった。私は寿司で、デスクはお造り。会話は特段、弾みもしなかったが、それを境に、おめえのデスクから怒られる時期は去ったように思う。
新人記者にとっての「本物の研修」は、そんな風にして終わった。だから、政寿司のロゴは忘れないのだ。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?