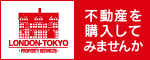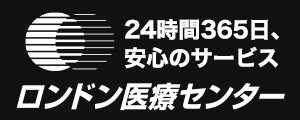第12回 「甘ちゃん」かもしれないが。
少し前、日本のある全国紙が新聞輸送の業者を切り替え、それが原因で宅配が大混乱に陥ったというニュースが流れていた。
英国に限らず、世界の多くの国では新聞の宅配制度がない。その点、新聞社ごとに自前の販売店を持ち、販売部数の9割が宅配される日本の制度は、やはり特殊である。そして当然のことながら、その仕組みは販売店で働く人が支えている。
ずいぶん古い話になる。
高校卒業時に大学入試に失敗した私は、東京・渋谷の朝日新聞販売店で働くことになった。四国から上京したのは、ちょうど今ごろの季節だったと思う。
店に紹介されたアパートは、人が階段を上るだけで振動が全体に伝わりそうな木造だった。2階の一番手前の4畳(4畳半ではない)が私の部屋で、隣が長野県出身の日雇いの60代の男、一番奥が板前の見習い。部屋の窓と隣のビルの壁は、わずかな距離しかなく、昼間でも電球をつけていた。
販売店の朝は早い。午前3時にはトラックが着き、店の前に梱包を放り投げる。梱包を解き、チラシの束と組み合わせて店を出発するのが朝4時で、配達終了は6時半。夕刊も午後3時にトラックが着いた。
私の持ち部数は350部ほどだった。販売店で夕食を終えると、数十種類のチラシの組み合わせを持ち部数と同じ数だけつくる。当時は自動折込機がなく、指サックをはめて、1種類ずつ抜き出し、チラシの束を手作業でつくっていた。
すべての作業を終わると、たいていは真夜中近くで、朝刊到着まで数時間しかない。空いた時間は集金と勧誘の手伝いである。
担当区域だった代官山は、今でこそ、「おしゃれな街」の代名詞になったが、当時は、しゃれた店もそろっておらず、裏に入ると、古ぼけたアパートもたくさんあった。
東京で最初の夏が近づいていたころだと思う。
あるビルで夕刊を配り終えて外に出ると、自転車が倒れ、新聞が風で乱舞していた。必死で拾い集めていると、ビル1階のブティックの若い女性に「汚い。早くきれいにして」と怒鳴られた。風の強い小雨交じりの日に倒れそうな場所に自転車を置いた自分が悪いのだが、道路の反対側にまで飛び、ゴミと化した新聞を拾い集めながら、無性に悔しかった。ものすごく孤独を感じていた。
店の若い同僚たちは「空手の師範を目指している」「ミュージシャンになる」などと、それぞれに夢を語っていた。だが、今思うと、彼らの多くは、それが叶わぬ夢になりつつあることに気づいていたのかもしれない。夢を語るにしては言葉に輝きはなく、それに向かって疾走している気配も感じなかったからだ。
1980年ごろからの1年余りは、そうやって過ごした。販売店とアパートとその周辺で、ぐるぐると時間が流れて行く。当時の良い思い出は少ししかない。その一つは、あるマンションの髭の管理人がいつも「君のような、汗をかく人が日本を支えているんだ」と励ましてくれたことだ。彼は、私が大学合格を報告したら、わざわざ渋谷のデパートでライターを買ってプレゼントしてくれた。
新聞はいま、大きな曲がり角にある。日本だけでなく、英国やその他の国々でも部数は伸びず、広告の落ち込みも激しい。「紙からネット・携帯へ」と媒体のシフトは急ぎ足であり、世界で希有な日本の宅配制度も大きな見直しは必至である。
でも、制度見直しは必然だとしても、心情的には、なかなかドライになれない。販売店の人たちは、どうするんだ、どうなるんだ、と。ネットの時代です、宅配は縮小します、みなさんご苦労さまでした、とはなかなか言えない。
日本では今朝も多くの販売店で一斉にみんなが動き始めている。30年ほど前の私と同様に先々の進路も分からぬまま不機嫌そうな表情ばかりする若い人。しわが目立つ近所のおばちゃん。やたらと手際がいい年配の男性。最近だと、東南アジアなどからの外国人も多いはずだ。
新聞業界だけではない。企業で物事を決める立場の人は、経営の指標や数字だけでなく、そんな、ふつうの人々にきちんと目を向けて判断を下してほしいと思う。「甘ちゃん」と言われるかもしれないが。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?