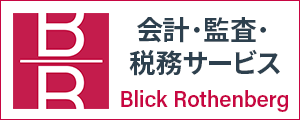リスクを取り得るのは誰か
世界経済の見通しが悪い中、改めて経済の基本を確認しておくのも悪くない。基本へ立ち返れば、見通せることと見通せないことの仕分けもしやすくなろう。
「経済が成長する」とは、付加価値(製品・サービスの売却価格と材料費の差、つまり世の中に対して新たに増えた価値が提供されたときの増加部分のこと)が増え続けるということを意味する。経済成長のためには、付加価値を増やすための不確実な事業に投資する人が必要だ。こうした投資を、不確実さを承知で出すお金という意味で「リスク・マネー」という。事業の主体が企業なら、投資は株式という形を取る。最近では複数事業を営む企業において、事業間のリスクの関係が不明確なので、事業を1つに絞った証券化商品の資本やメザニン部分(資本と負債の中間)を購入するという形の投資が流行った。
しかし、サブプライム・ローン問題で証券化商品の価格が暴落し、実体経済の悪化から企業の業績が落ちる、すなわち付加価値が増加しないという見通しが一般化するにつれて、リスク・マネーの量は急激に落ち込んでいる。リスク・マネーを引き揚げられたり、追加出資を受けられない企業の倒産が増えつつあることがこれを示している。
リスクを取れるのは、余裕のある人、失敗しても生活に困らない人である。すなわち現在なら個人、お金持ち、国家(ソブリン)だ。よく個人向けの投資ガイドなどが、「今年は株式の買い時だ」などと煽るのは、たとえ回収金がゼロになっても、個人は他に給料からの所得があれば生活できるという前提があるからだ。(言い換えると、株に生活資金そのものを注ぎ込んではいけない)。またサウジアラビアの王族やオーナー会社の社長などの富裕層も投資を行っている。(サラリーマンが資産運用を担当している機関投資家は、思い切った投資はできない)。さらに国家の資産運用主体においても、中国が米国債を買うなど活発な動きをしている。
それでも足りない資金
こうした個人、金持ち、国家によるリスク・マネーに以前のような潤沢さはもう見られず、資金量は極めて少なくなっている。だからキャッシュの価値が増すし、キャッシュを無尽蔵に出せる中央銀行に期待がかかる。また、国家の財政政策にも強い期待が寄せられている。
しかし、中央銀行の金融政策や国家の財政政策は、ケインズが指摘したように短期的に経済を成長させても、すなわち付加価値の増加を助けても、長期の成長をサポートするものではない。長期の成長は、人口増加、設備投資などの社会資本増加、技術革新などが決めていくものだ。こうした成長のための投資を行うのは、社会インフラ部分は財政、技術や設備については民間企業の役割である。だがその資金を民間企業に融資するリスク・マネー、すなわち、資本や負債性資本(優先株、劣後債)などが不足している。
リスク・マネーの行方
では金利が低下している中、リスク・マネーはどこに行ったか。それは米国債である。米国への信頼はまだまだ厚い。だから対円はともかく、対ユーロではドル安にはさほどなっていない。ユーロは出来て日が浅い。経済が上り調子のときは信頼を得ていたが、下り調子においてはまだ試されていない。EU各国の財政分担がバラバラで、最終的にどの国がどれだけ負担するかは、経済的にも政治的にも、もちろん法的にも決まっていない。その上アイスランドや英国も通貨圏に入り実質的に補助を得ようという議論があるなど、経済的に弱い国にぶら下がられてしまっては、ますます負担のシェアが問題になるだろう。ユーロはこれからが正念場だ。
結局、米国債から金がどこにも向かわない状況下では、各国の中央銀行がいくら流動性を供給しても、リスク・マネーの争奪戦になる。こうしたリスク・マネー不足という状況は、戦後すぐの日本にもあった。戦争で負けたため日本は海外から借金ができず、政府は資金割当を行った。石炭や鉄鋼を優先する傾斜生産方式、日本銀行の窓口指導、旧通産省の業界指導といった統制経済の下で、付加価値を上げやすい産業に集中的に資源投下し、朝鮮戦争の特需で日本は高度成長の波に乗った。今回も、戦争の誘惑はともかくとして、資金割当を担う各国政府や銀行に良き人材を得た国が栄えることになろう。
さて日本は、英国はどうであろうか。人を得ず、国の方向性が定まらない日本の政治の体たらくは致命的ではないか。
(2009年1月9日脱稿)
| < 前 | 次 > |
|---|

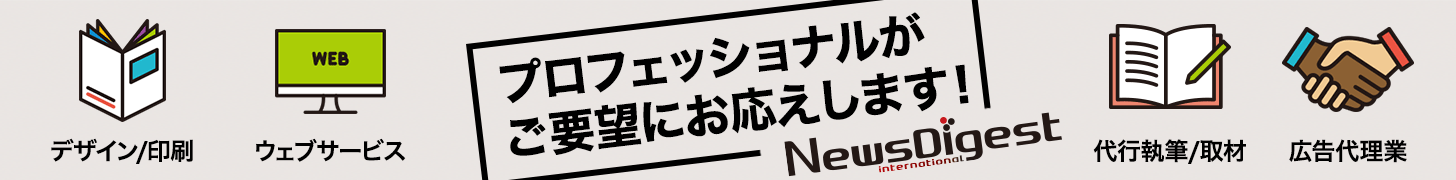

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?