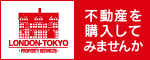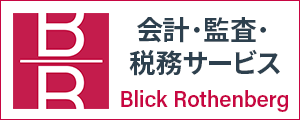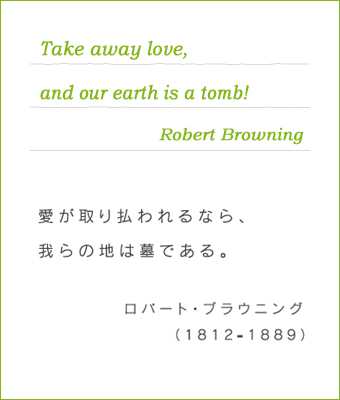
病弱のエリザベスから真の自分を愛してと懇願され、その彼女と共にイタリアに駆け落ちしたロバート。初めはピサに居を構えたが、後にルネサンスの都・フィレンツェに落ち着いた。至上の愛を貫くふたりは、人間復興の町という格好の舞台を得たのだった。
人間として真に生きることを得たに留まらない。燃え上がる愛のさなかに、それぞれ詩魂のほとばしるままに愛の詩を綴った。エリザベスは詩集「ポルトガルからのソネット」を、ロバートはその名もずばり「男と女」という詩集を世に出す。前回の名言も今回のものも、ともにイタリアで編まれたそれぞれの愛の詩集から引いたものだ。
ふたりの愛の邪魔となるものは何もなかった。生活のための仕事があるわけでもない。愛を純化し、鎧に固めたような黄金生活を、ふたりは生きた。生きることは愛することであり、愛することは生きることだった。まさしく、愛がなければこの世は闇、地は墓と化す。ロバートは、詩の世界でも、エリザベスと愛の谺(こだま)を返し合った。
ブラウニング夫妻に倣うわけではないが、至純の愛を全うしたかったら、手に手をとるようにして、外国にでも脱出すべきかと思う。外国が許されぬなら、山奥にでも籠もるがよい。外界からの干渉を徹底して退け、隔絶されたふたりの世界に浸りきるのだ。朝から晩まで片時も離れず、ひとつ繭にくるまるようにして暮らす。寝ても醒めても、互いの息が届くほどの距離に始終いなければならない。そんなしんどい、息が詰まるとおっしゃる御仁は、失礼ながら、至上の愛には縁のない方だろう。スペインの天才画家ダリは、掠奪愛によって我がものとした新妻ガラと、ホテルの部屋に何カ月も籠もりきり、一歩も外に出なかったという。いかにも奇矯の人ダリらしいエピソードだが、これもやはり愛の砦への籠城だったに違いない。
現代は、愛に生きることが難しい時代だ。男女ともに、仕事が待っている。携帯に電話はかかってくる。メールのチェックもある。テレビがふたりの間にたちはだかり、会話を奪う。仲のよい夫婦やカップルはいても、ブラウニング夫妻のような全人格的にして絶対的な愛は、ノスタルジアの対象になってしまった気がする。互いの間に一切の夾雑物(きょうざつぶつ)を認めず、凸凹のぴたりと合わさったまま偕老同穴(かいろうどうけつ)を貫く絶対値としての愛は、21世紀の今ではもはや神話だろう。
フィレンツェに行けば、ブラウニング夫妻の暮らした家は観光スポットとなっている。愛を鎧と固めて巣籠もりすることは難しくとも、やはり人は至純の愛に憬れる。かなわぬ夢と知りつつ、人は夫妻の愛の威光にすがろうとするのかもしれない。
| < 前 | 次 > |
|---|



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?